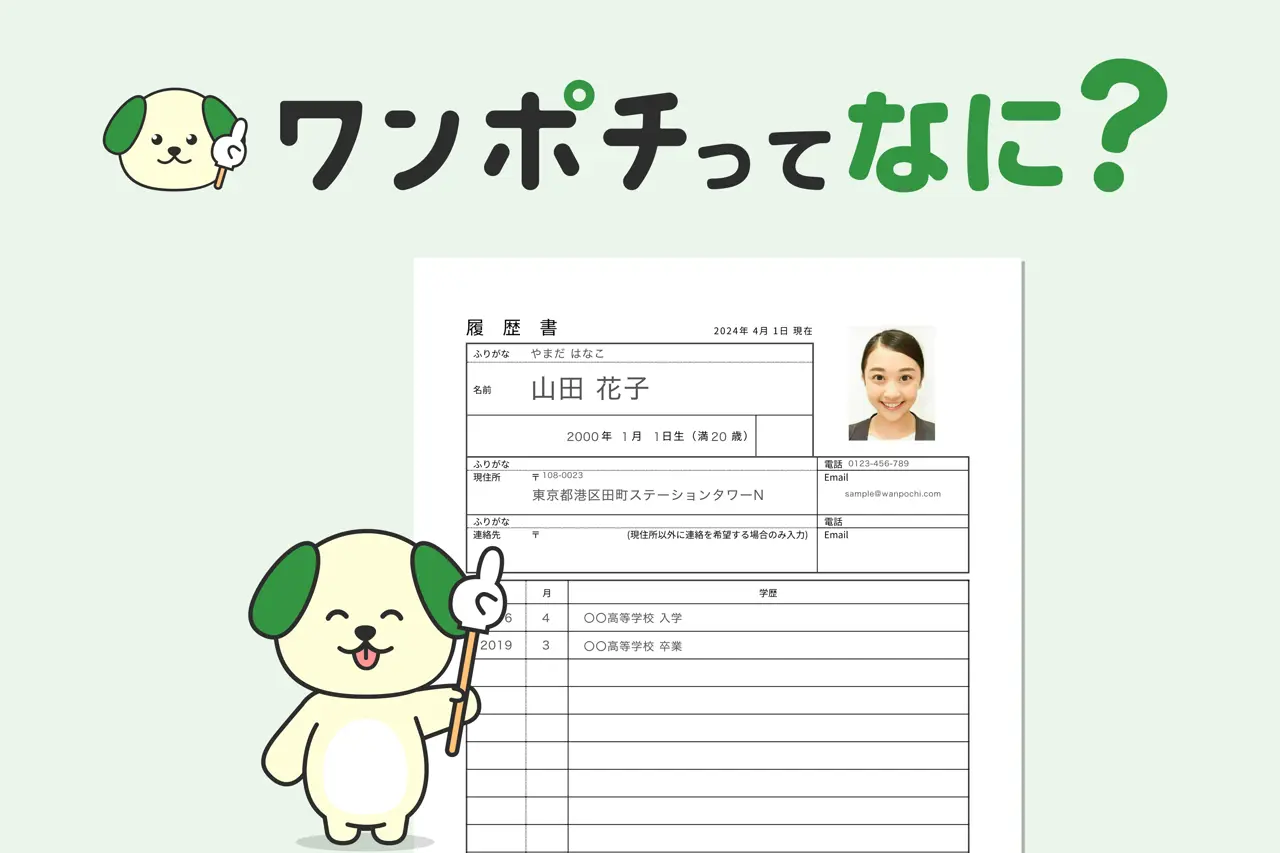職務経歴書の枚数は何枚が最適?具体的な枚数と記入例を解説

職務経歴書は履歴書と異なり、決まった書式があるわけではありません。しかし、採用担当者に好印象を与えるためには、全体の文章量や項目といった基本的なルールを意識することが大切です。
今回は職務経歴書をどのくらいの枚数でまとめるべきなのか、どのような項目が必要になるのかについて、具体的な記入例とともにご紹介します。
この記事を読む前に「基本の職務経歴書の書き方が知りたい」という人は先にこちらをチェック!
関連記事:【47種類】職務経歴書の書き方とテンプレート・例文|基本ルールも紹介
職務経歴書は1~2枚程度で作成する

職務経歴書は「A4 サイズ1~2枚程度」で作成するのが基本です。まずは、職務経歴書の枚数が多い・長すぎるとNGな理由と、職務経歴書が短すぎるとNGな理由について解説します。
職務経歴書の枚数が多い・長すぎるとNGな理由
枚数が多すぎれば、読み手である採用担当者の負担が大きくなり、細部まで読み込んでもらえない可能性が出てきます。採用担当者は応募者ごとに複数の書類に目を通す必要があるため、長すぎればマイナスの印象につながる恐れがあります。
また、「伝えたい意図をまとめられていない」「要点を絞り込めない」「読み手を意識できていない」と、厳しい見方をされてしまうケースもあるでしょう。
職務経歴書が短すぎるとNGな理由
反対に、短すぎても「熱意が感じられない」というネガティブな印象につながる恐れがあります。職務経歴書では、自身のキャリアや経験を通じて、応募先の企業でどのように活躍できるのかを示す場です。
極端に短ければアピール不足になってしまうので、過不足のない適切な情報量でまとめることを心がけましょう。
職歴が少ない場合の対処法

次に、職歴が少なく、十分なアピール材料がないときの対処法について見ていきましょう。
職歴以外の経験を強調する
職歴が少ないときには、アルバイトの経験を書くのも1つの方法です。仮に短期間のアルバイト経験であっても、担当していた業務内容やスキルがあれば、具体的に書いてみましょう。
特に、応募する職種や業務に関連する経験であれば、積極的にアピールしていくことが大切です。また、ボランティア活動やインターンシップでの経験を書くのもよいでしょう。
ボランティア活動で得られた経験やスキルを書くことで、社会貢献への意欲やコミュニケーション能力をアピールできます。インターンシップの経験で培われた知識や経験は実務経験として評価されることがあるので、具体的な業務内容や成果を書いて、どのような経験をしたかをアピールしてみましょう。
関連記事:アルバイトから正社員を希望する際の履歴書の書き方は?
スキル・能力を具体的に記述する
業務経験が少なく、書くことがあまりないと感じる場合でも、職務経歴書では決して手を抜くべきではありません。応募する職種に応じた経験がないか改めて洗い出し、きちんとアピールできるように内容を充実させることが大切です。
たとえば、第二新卒の若手であれば、ポテンシャルが重視されることも多いです。十分な業務経験や実績がなくても、コミュニケーション能力やプレゼン能力、リーダーシップのヒューマンスキルが自己PRの材料となります。
また、新卒で入社してから得られた経験や、研修で学んだことも盛り込めるでしょう。たとえば、「業務と並行して半年間の営業研修を受けたので、法人営業の基礎知識は身についている」や、「1ヶ月間の店舗実習を受けたので販売業務に活かしたい」といったように、どのように実務に活かせるかを主体的に表現するのがコツです。
関連記事:第二新卒向け職務経歴書!書き方のコツやフォーマットを紹介
具体的なエピソードを交えて書く
自身のスキルや強みを伝える際には、具体的なエピソードを交えると説得力が生まれます。第二新卒で社会人経験が短いときは、業務経験以外のテーマを取り上げて、アピール材料とするのもよいでしょう。
具体的には、留学経験を通じた語学スキルやコミュニケーション能力、大学での研究を通じた専門知識も強みとして表現できます。応募先の企業が求める人材像を把握し、相性の良い特徴をピックアップして、自己PRに活用しましょう。
関連記事:履歴書への「留学経験」を書く正しい方法と短期留学のアピール方法
「なぜ」「どのように」を明確にする
経験したことをそのまま書いても、採用担当者にはイメージが伝わりづらいでしょう。仕事やボランティア活動、インターンシップといった経験を通じて、「なぜ」行動したのか、「どのように」課題を解決したのかを具体的なエピソードを交えて書いてみましょう。
きちんと理由を説明することで、考え方や行動へのプロセスが伝わり、採用担当者の目に留まりやすくなるといえます。
職務経歴書を1枚にまとめるときのポイント

職務経歴書を1枚に整理するには、レイアウトを工夫する必要があります。具体的には、まず箇条書きや表を活用してみましょう。
文字だけ伝えるよりも、箇条書きや表を積極的に活用することで、情報が整理されて読みやすくなります。大事な箇所を太字や下線で強調すれば、より効果的です。
また、フォントと文字サイズに意識を向けることも大切です。職務経歴書の全体的なバランスを考慮しつつ、適切なフォントや文字サイズを選ぶことで、統一感のあるレイアウトに整えられます。
そして、適度に余白をつくることも重要です。余白が少なければ、情報が詰まった印象を与えてしまうため、読みやすさを重視して余白をとってみましょう。
職歴が多すぎる場合の対処法

職務経歴書では、職務経歴や職務内容がメインの情報となります。転職を重ねていて職歴が多いときは、適度に調整して長くなりすぎないようにまとめることが重要です。
応募先の企業に合わせて経験やスキルを整理する
職歴が収まりきらないときは、応募先の企業に合わせて、優先度の高いものを取捨選択するのがコツです。単に情報を羅列するだけでは、読み手を疲れさせてしまうため、伝えたい情報を絞り込んでまとめるようにしましょう。
また、情報を適切に伝えるためには、表現方法に強弱をつけることも肝心です。応募する業種・職種と関連性の薄い経験やスキルは、できるだけ1行に要約し、さらっと読めるようにまとめましょう。
そして、本当に伝えたい職歴や経験、スキル、強みに焦点を当てて、重点的に記載することが大切です。そのうえで、職歴や実績を紹介するときには、箇条書きや数字を使って、分かりやすく整理するのもポイントです。
関連記事:履歴書の作成時に職歴を忘れてしまった時の対処法は?
転勤や異動が多い場合も経験やスキルを中心にまとめる
職務経歴書では、今までに勤めてきた企業ごとに情報をまとめるのが基本です。しかし、転職や異動が多く、経験社数や経験部署数が多いときは、スキルや経験で括って紹介するのも1つの方法です。
たとえば、さまざまな企業で営業職を経験したのちに、現在は管理職として働いている方は、「営業に関する経験」「マネジメントに関する経験」といったテーマ別に職歴を整理するほうが見やすくなります。各勤務先や部署に所属していた期間を併記すれば、業務ごとの経験年数も明確になるため、自身の強みが伝わりやすいでしょう。
別紙資料を検討する
職歴が多く、どうしても書いておきたい実績やスキルがあるときは、別紙資料としてまとめることを検討してみましょう。別の紙にまとめることで、職務経歴書をすっきり整えられます。
別紙資料を作成するときは、職務経歴書との関連性を明らかにして、分かりやすさを重視することが大切です。
職務経歴書が3~4枚になってしまうときの書き方

職務経歴書の枚数が多くなってしまうときは、記載する情報に優先順位をつけたり、職務要約を活用したりすることが大切です。各ポイントについて見ていきましょう。
情報の優先順位をつける
まず、職務経歴書をまとめるときには、応募先の企業に合わせた情報をピックアップしていくことが重要です。求められている人材像をきちんと把握したうえで、必要とされるスキルや経験を優先的に書き、あまり関連性のない情報は思いきって削ってみましょう。
適切な情報を記入するには、応募先の企業をしっかりと研究して、ニーズを把握することが大事です。また、今までの経歴を振り返って、最も成果をあげたプロジェクトや貢献度の高い実績を絞り込んでみましょう。
具体的なエピソードや数字を用いれば、実績を客観的・定量的に示すことができるので効果的に情報を伝えられます。
職務要約を活用する
職歴が多いときは、職務経歴書の冒頭部分に職務要約を記載してみるとよいでしょう。今までのキャリアの概要を3~5行ほどにまとめて、大まかな職歴が伝わるように工夫することが大切です。
職務要約を作成するときは、応募先の企業が求める人材像に合わせて、アピールポイントとなる情報を強調して書くと効果的です。
関連記事:職務経歴書の職務要約・職務概要とは?例文と上手にまとめるポイントを解説
職務経歴書の枚数は1~2枚に過不足なくまとめよう

職務経歴書の枚数は、A4用紙1~2枚程度に収めるのが適切です。長すぎれば採用担当者の負担になってしまう一方で、短すぎても熱意がうまく伝わらない可能性があります。
職務経歴書を作成する際には、まず全体像に目を向け、どのような内容を記載すべきなのかを丁寧に理解しましょう。そこから各項目を書き始めれば、それぞれのボリューム調整が行いやすくなります。
履歴書作成サービスの「ワンポチ」では、PC・スマホからの操作で手軽に履歴書・職務経歴書を作れます。各種書類のフォーマットから、ケース別の自己PR・志望動機のテンプレートまで、作成に必要なデータや機能が豊富にそろっています。
履歴書・職務経歴書の作成には、ぜひワンポチをご利用ください。
ワンポチで履歴書を作成してみたい方はこちら!
履歴書 を作成してみる
ワンポチで職務経歴書を作成してみたい方はこちら!
職務経歴書 を作成してみる
職務経歴書の基本的な書き方
職務経歴書に記載する項目の詳しい書き方は下記ページでご紹介していますので、ご参照下さい。
⑩職務経歴書は何枚書く? |