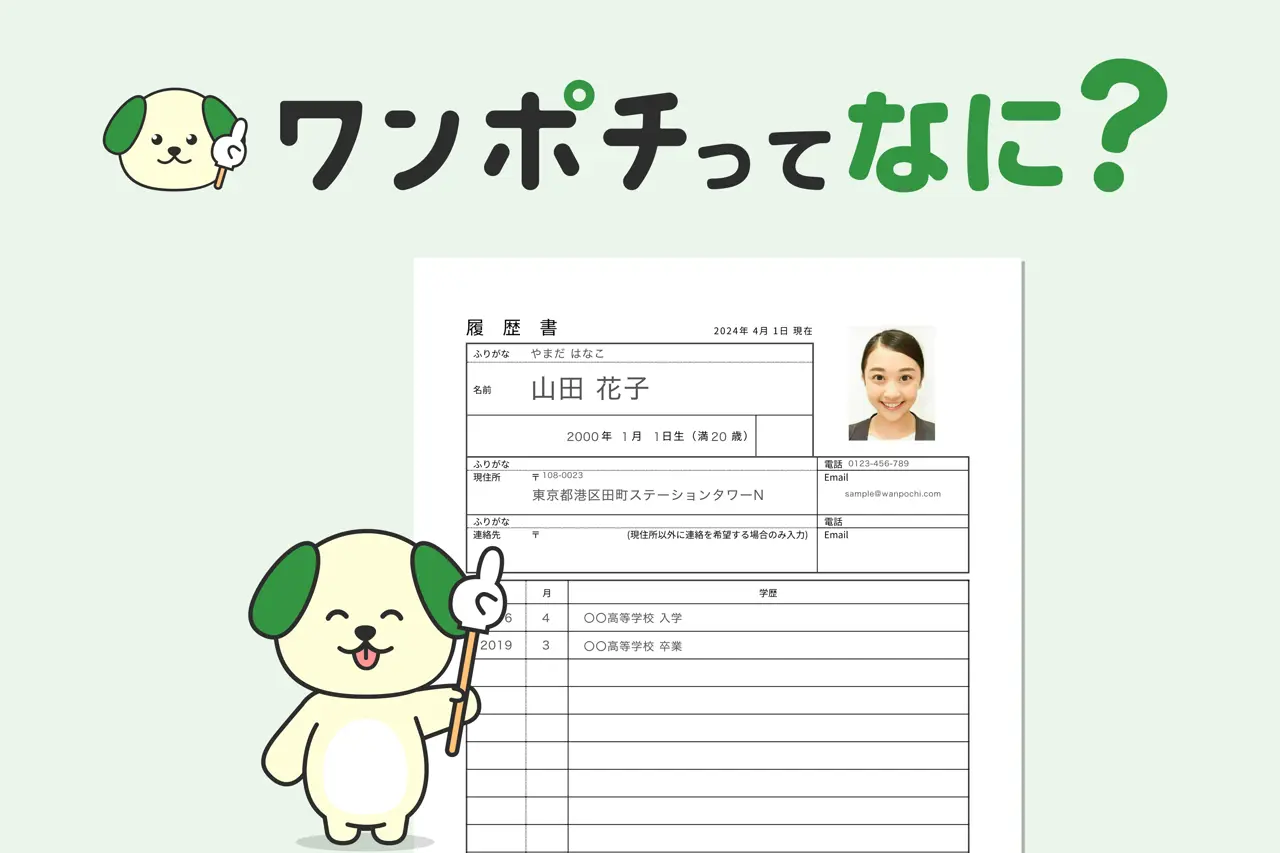履歴書の資格・免許はどこまで書く?正しい書き方とポイントを解説

履歴書には自身が保有している資格や免許を記載する欄があります。資格・免許は業務に必要なスキルや知識を持っていることを証明できる項目であり、自身の強みをアピールするための武器にもなり得ます。
記載にあたっては基本的なルールをきちんと把握して、適切な形でアピールできるようにすることが大切です。今回は、履歴書の「免許・資格欄」の書き方と注意すべきポイントについて解説します。
この記事を読む前に「基本の履歴書の書き方が知りたい」という人は先にこちらをチェック!
関連記事:【16種類】履歴書の書き方・テンプレートを解説!基本的なルールと文例を紹介
履歴書に資格や免許を書くときの基本的な5つのルール

資格や免許の欄は、自身のスキルや仕事に必要な資質を示す重要な項目です。採用担当者にしっかりとアピールするためにも、端的に分かりやすくまとめることが求められます。
ここではまず、資格や免許を記載するときの基本的なルールを5つに分けてご紹介します。
資格や免許は正式名称で記載する
免許・資格は省略せずに、正式名称で書くのがルールです。免許や資格の正式名称は長いものが多く、普段の会話では省略された名称が用いられることがほとんどなので、きちんと調べておくとよいでしょう。
たとえば、一口に「運転免許」と言っても、後述するようにさまざまな種類があります。職種によっては、特定の運転免許が必須となるケースもあるため、誤りがないように記載することが大切です。
そのほかの例を挙げれば、経理業務の代表的な資格である「簿記」も、日商簿記、全経簿記、全商簿記の3種類があり、級別の区分もさまざまです。自身の情報を正確に伝えるためにも、合格証書や主催団体のホームページの情報をもとに、正しい資格の名称をチェックしておきましょう。
また、免許・資格については取得年月も記載する必要があります。種類によっては試験の内容や難易度が途中で変わっていたり、有効期間が設けられていたりするものもあるので、取得年月も正しく記載しましょう。
運転免許の書き方
免許・資格の記入順序については、特に決められたルールはありません。しかし、運転免許と他の資格は分けてまとめるほうが、スッキリと読みやすくなるでしょう。
車の運転を行う職種であれば、先に免許をまとめて書くのが望ましいです。まずは運転免許を取得順に書いて、その後にほかの免許・資格を続けて記載しましょう。
なお、運転免許については、AT限定やペーパードライバーの場合でも記載して問題はありません。
和暦・西暦を統一する
免許・資格欄ではそれぞれ取得した年月を記載する必要があります。年表記については、和暦と西暦のどちらで記載しても構いませんが、読みやすさを考慮してどちらかに統一するのが基本です。
履歴書は横書きであるため、特にこだわりがなければ西暦を用いるほうがよいでしょう。和暦は、年号が切り替わったタイミングや「元年」表記の注意点が増えるため、西暦のほうがスムーズに記載できるはずです。
なお、年月の表記には算用数字を用いましょう。
関連記事:履歴書の生年月日の書き方|基本的なルールと記入例を解説
業種・職種に関連した資格・免許を優先する
先にも述べたように、免許・資格の記載は決まった形式はなく、取得した順に書いていけば問題ありません。ただし、応募する業種や職種に関連のない資格・免許を並べても、自身をアピールする効果は薄くなってしまいます。
複数の免許・資格を持っているときは、関連したものを優先して記載するのがコツです。また、記載するかどうか迷う場合は、何が好印象につながるかは分からないため、関連性が判断できなくても書いておくほうがよいでしょう。
免許・資格を持っていない場合
特に免許・資格を持っていないときも、空欄にはせず「特になし」と記載するようにしましょう。空欄のままだと、記載漏れと誤解を与える可能性もあるため、きちんと記載したほうが親切です。
また、現在取得に向けて勉強中の免許・資格があり、業務に関連性が高いものは「○○受験予定」と記載してもよいでしょう。
履歴書の資格の書き方とポイント

資格の書き方については、前述した基本的なルールを守るとともに、細かな表記方法にも気を配ることが大切です。ここでは、履歴書に記載する際に気をつけたい注意点をご紹介します。
業種・職種に合った資格から記載する
資格については、応募先企業の業種や、自身が希望する職種との相性を踏まえて記載順を検討することが大切です。たとえば、事務職であれば「日商簿記」や「MOS(マイクロオフィススペシャリスト)」、「ITパスポート」「秘書検定」「TOEIC」といったものが、親和性の高い資格として挙げられます。
先に資格を記載しておき、その後にほかの免許・資格についてまとめていくとアピールをスムーズに行いやすいでしょう。また、取得年月も評価ポイントとなるので、正しく記載する必要があります。
合格や取得の表記は種類に応じてかき分ける
免許・資格を取得したことを示すためには、1文字分のスペースを空けて、種類に応じた適切な表記を行う必要があります。一般的に、免許証が公布される免許・資格については、「取得」が正しい表記です。
具体的には自動車の運転免許や危険物取扱者の免許、税理士、弁護士の免許は取得と表現します。一方、一定の基準をクリアしたことが証明される検定資格は、「合格」が適切な表記です。
たとえば、簿記検定試験やファイナンシャルプランナー(FP)、医療事務、秘書検定は、合格を用いるのが一般的です。また、免許のなかには、特定の教育訓練の「修了」が条件となっているものもあります。
たとえば、建築現場や倉庫内作業で必要とされるフォークリフトに関する資格では、技能講習を受講して試験に合格したなら「フォークリフト運転技能講習 修了」、特別教育を受講したときには「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 修了」が正式な表記です。正しい表記は、主催団体のホームページに記載されているので、必ず確認しましょう。
また、複数の区分が設けられている資格については、合格した級についても記載することが大切です。
関連記事:【施工管理】履歴書の書き方のコツ!志望動機のポイントも解説
勉強中でも記載してよい
履歴書では、まだ取得していない資格であっても、現在勉強中であるなら記載することが可能です。応募先の企業によっては、資格の重要性や難易度を踏まえて、プラス評価につながる可能性があるでしょう。
また、複数の級が設けられている資格について、上の級の勉強を進めているときは、上位資格の取得に向けて勉強していることをアピールするのも1つの方法です。取得予定や受験時期が分かっていれば、タイミングについても併記しておきましょう。
履歴書の免許の書き方とポイント

免許を記載するときも、基本的には資格と同様の注意点を守ることが大切です。ここでは、免許の記載方法と意識すべきポイントを見ていきましょう。
免許は正式名称で記載する
免許についても、略称ではなく正式名称で記載する必要があります。特に建設機械や重機、車両の運転免許は、どの区分のものを取得しているかによって、扱える機械が変わります。
職種によっては、免許の細かな区分でも評価が変わることがあるため、必ず正式名称で記載しましょう。免許の正式名称は、免許証が手元になければ主催団体のホームページでも確認することができます。
主な運転免許の種類
一般的に免許といったときは、運転免許のことを指すことが多いです。主な運転免許の正式名称を確認しておきましょう。
一般的な略称 | 正式名称 |
大型免許 | 大型自動車免許 |
中型免許 | 中型自動車免許 |
準中型免許 | 準中型自動車免許 |
普通免許 | 普通自動車免許 |
大型バイク免許 | 大型自動二輪車免許 |
中型バイク免許(中免) | 普通自動二輪車免許 |
原付免許 | 原動機付自転車免許 |
他の資格・免許よりも優先して書く
資格や免許は取得順に時系列で書くのが基本とされていますが、アピールしたいものから優先的に記載するのも1つの方法です。たとえば、仕事に車やバイクを使う職種では、どの免許を取得しているかが重要な採用基準となるケースもあります。
仕事で必要な場合は、求人情報にも「要普通免許」「普通免許保有者優遇」といった記載があるはずです。運転免許を先に記載して、きちんと採用担当者の目に留まるように工夫するとよいでしょう。
ただし、特に車やバイクの免許がいらない仕事であれば、無理に記載する必要はありません。事前に採用条件を確認しておき、該当する免許を持っているかどうかチェックしましょう。
関連記事:運送業の履歴書の書き方は?職種別の例文やポイントを紹介
履歴書の資格・免許に関するQ&A
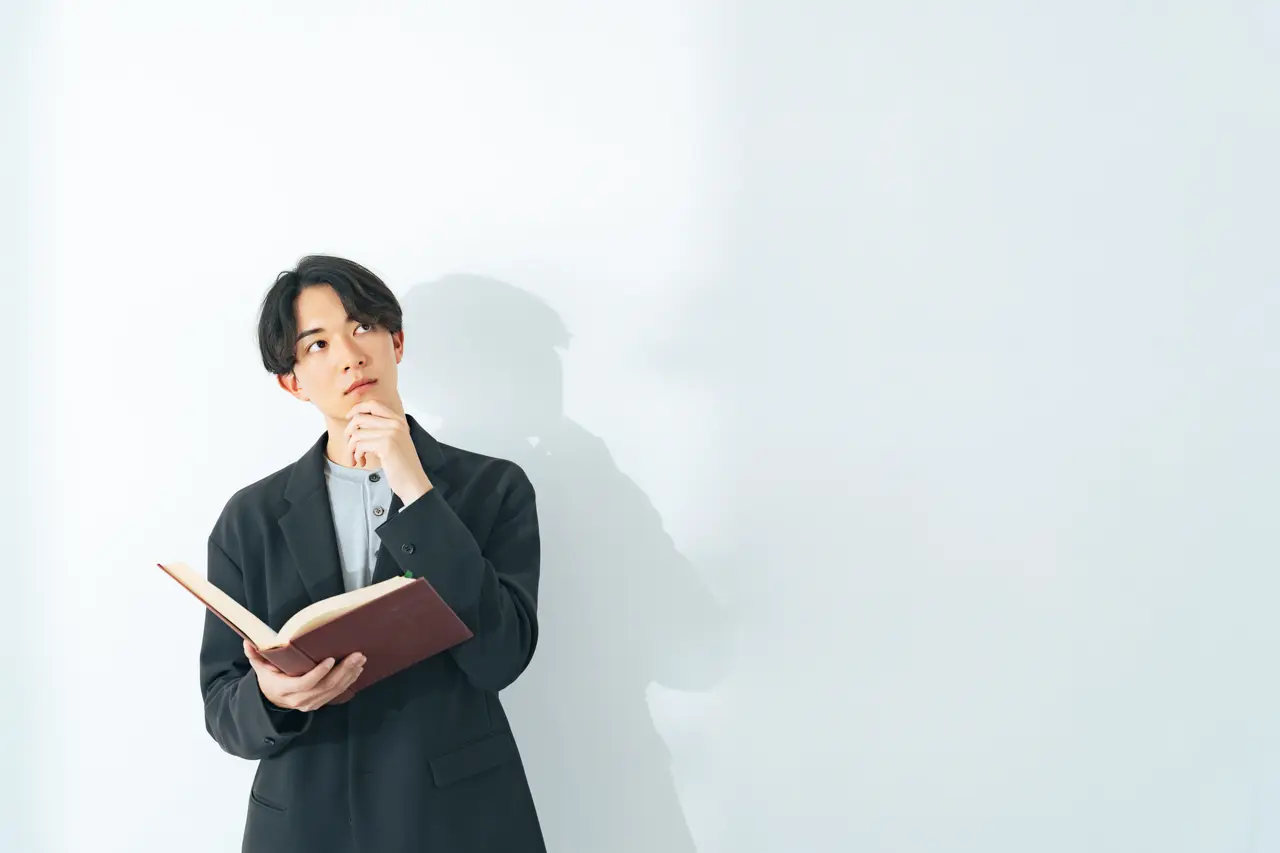
最後に、ここまでの内容も踏まえながら、履歴書の免許・資格欄に関するよくある質問を確認しておきましょう。
資格は何級から書いていい?
資格によっては、複数の級が設けられているものもあります。同一の資格であれば、取得しているなかでも上位の級のみを記載するようにしましょう。
また、記載する資格の種類により、どの級からがアピール材料になるかは異なります。たとえば、英検であれば、2級以上でなければ英語力をアピールするのは難しいといえます。
英検3級や準2級については、免許・資格欄に余裕がなければ、優先して記載する必要はないといえるでしょう。また、金融系の職種においては、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格が役立つケースも多いですが、2級以上が歓迎要件・必須要件となっていることがほとんどです。
下位資格にあたる3級を取得しており、2級の取得を目指しているときは、勉強中であることを踏まえて丁寧に記載するとよいでしょう。いずれにしても、資格を効果的にアピールするためには、応募先の募集要項をチェックすることが大切です。
書かないほうがよい資格とは?
基本的に、免許・資格欄は自身のスキルや能力を証明するための項目です。そのため、特に業務に関係がない資格は、あえて記載する必要はないといえるでしょう。
たとえば、遊びやスポーツに関する資格は、どちらかと言えば趣味性が強いとされるため、他の資格より優先して記載すべきではありません。ただし、記載することで自身の人となりをアピールできる可能性があるときは、特技・趣味欄に書いておくとよいでしょう。
場合によっては、面接時のトークテーマとして活用できる可能性もあります。
関連記事:履歴書の特技欄の書き方|文例とアピールポイントを解説
欄に資格が書き切れないときはどうする?
履歴書のなかでも、免許・資格欄のスペースは一般的に5~6行程度であり、あまりスペースがあるわけではありません。さまざまな資格を取得していて、既定のスペースに書き切れないときは、優先させたい順に記載することが大切です。
すべての資格や免許をアピールしたいときは、別紙参照として免許・資格用の資料を添付する方法もありますが、単に保有している資格や免許の数を知ってもらうだけではプラスの評価につながりません。むしろ、より重要性の高い経歴や経験、志望動機を知ってもらえる機会が損なわれてしまうので、無理にアピールするのは好ましくないといえるでしょう。
資格をしっかり記入してアピール力のある履歴書を作成しよう

履歴書の免許・資格欄は、業務の必要なスキルや知識を持っているかを簡潔にアピールする重要な項目です。また、応募先によっては、保有している免許・資格の希少性、特殊性をもとに、プラスの評価が得られるケースも少なくありません。
自身の保有しているスキルを正しく知ってもらうためにも、記載する際には基本的なルールや正式名称を把握しておく必要があります。適切な方法で記載するためにも、チェックを怠らないように注意しましょう。
履歴書作成サービス「ワンポチ」では、PC・スマホから無料で履歴書・職務経歴書が作成できます。新卒・転職・アルバイト等のシーン別フォーマットが用意されており、自己PRや志望動機のテンプレートもそろっています。
効率的な履歴書作成にぜひお役立てください。
ワンポチで履歴書を作成してみたい方はこちら!
履歴書 を作成してみる
履歴書の基本的な書き方
履歴書の項目・欄ごとの詳しい書き方は下記ページでご紹介していますので、ご参照下さい。
⑥免許・資格欄の書き方 | |