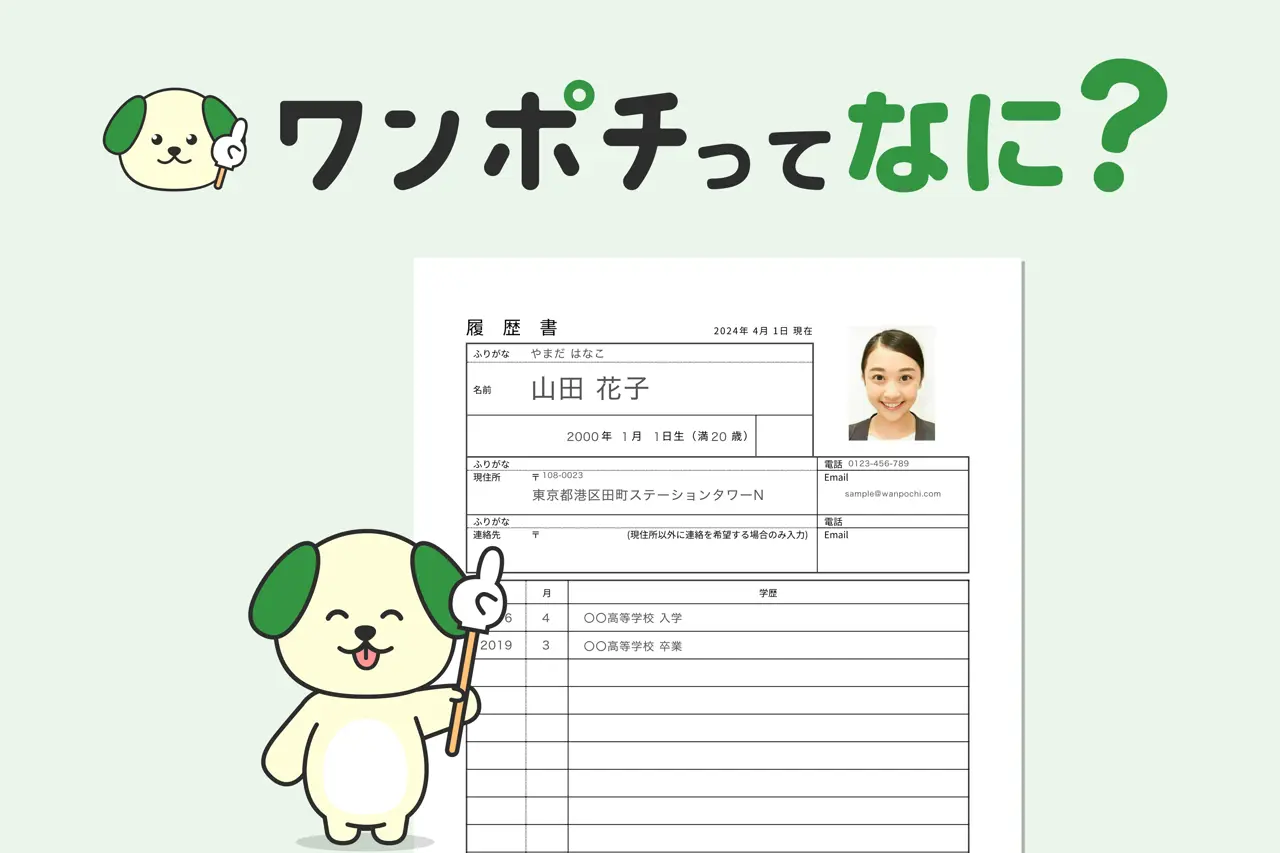児童支援員の職務経歴書の書き方と例文!ポイントや注意点も紹介

児童支援員としての就職・転職を目指す際、重要となるのが職務経歴書です。これまでの経験やスキルを効果的に伝えられるかどうかで、採用の可否が左右されることがあります。しかし「どのように実績をアピールすればよいのか」「未経験でも魅力的に書けるのか」と悩む方も多いでしょう。
本記事では、児童支援員の職務経歴書の書き方や例文を詳しく解説します。自身の経験を活かし、採用につながる職務経歴書を作成するための参考にしてください。
この記事を読む前に「基本の職務経歴書の書き方が知りたい」という人は先にこちらをチェック!
ワンポチには児童支援員向けの職務経歴書テンプレートがあります。簡単に作れる職務経歴書に興味がある方は、ぜひ一度お試しください。
児童支援員の職務経歴書を書く時のポイント
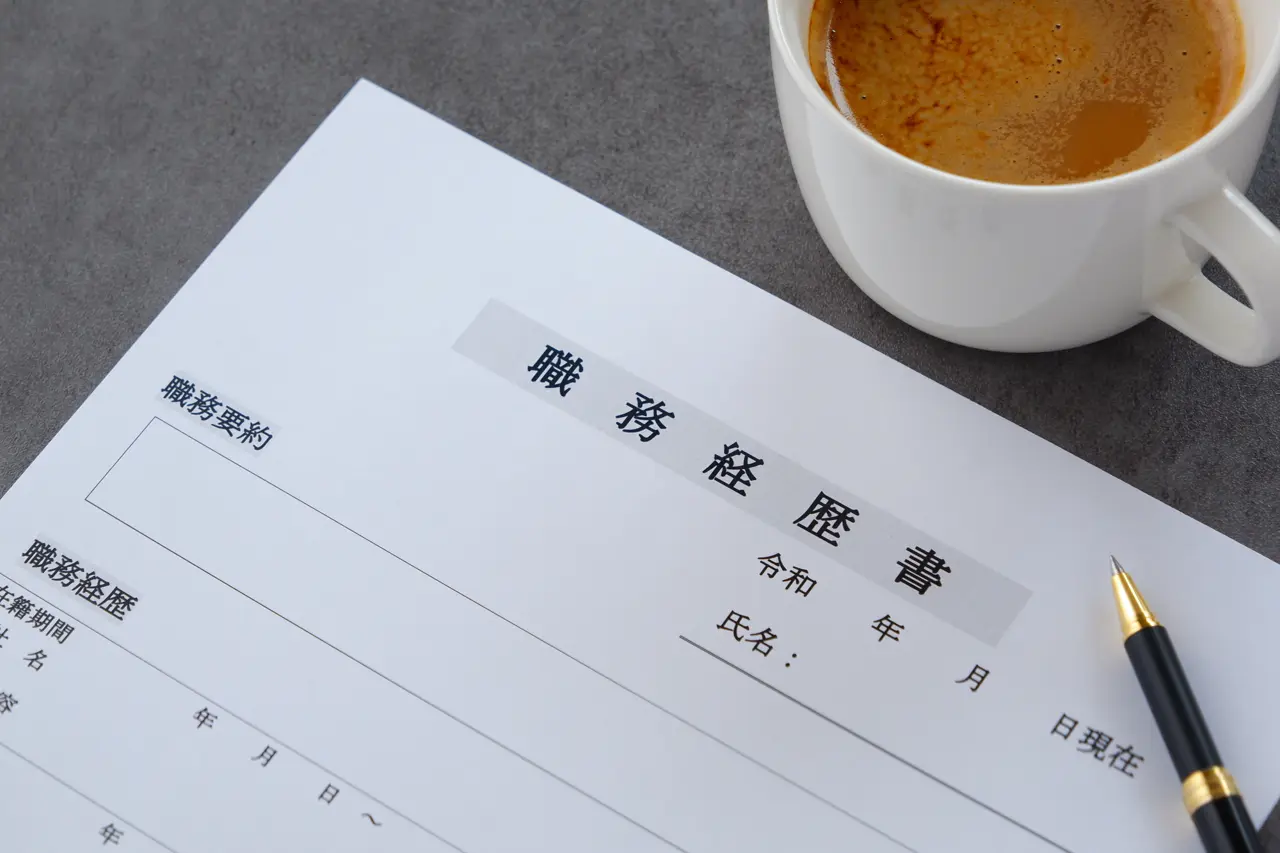
職務経歴書を書く前に、ポイントをしっかり把握しておきましょう。ここでは、児童支援員の職務経歴書を書く時のポイントを解説します。
資格・スキル欄で児童支援員としての専門性を明確に示す
児童支援員としての専門性を明確にするためには、保育士や社会福祉士、教員免許などの必須資格を記載しましょう。記載する際、正式名称と登録番号、取得年月を明記する必要があります。
また、児童指導員任用資格に該当する学歴や経験も具体的に書きましょう。たとえば、大学・専門学校の学部や学名、実務経験年数などです。
研修受講歴を書く際は、研修名や主催団体、受講期間・内容を具体的に記載しましょう。専門性を高める研修受講歴は、児童発達支援や障がい児保育、虐待防止があります。
得意な支援・スキルを専門的に記載するのも可能です。支援の種類は以下のとおりです。
職務経歴書に記載可能なスキル
・発達支援
・障がい児支援
・心理・行動支援
・学習支援
・多文化理解
発達支援では、個別支援計画作成の経験、TEACCHやPECSなどの支援方法、発達段階に応じた遊びや活動の提供、記録・評価の経験を詳しく記載します。
障がい児支援では、障がいの種類に応じた具体的な支援経験や医療機関や療育機関との連携経験、合理的な配慮の提供を具体的に書きましょう。
心理・行動支援では、子どもの心理状態の理解や気になる行動への適切な対応、アタッチメント形成への配慮などを具体的に記載します。
学習支援では、発達に合わせた教材の選定・作成や、個別・集団での学習支援経験、学習意欲を引き出す工夫などを具体的に書きます。
多文化理解について書く際は、 外国籍の子どもや保護者への支援経験、多文化共生に関する知識などを具体的にするとよいです。
職務経歴欄で児童支援員としての具体的な支援内容と子どもの成長を語る
児童支援員の職務経歴書を書く場合、勤務先の種類と対象となる子どもの年齢層、障がいの有無、支援の目的などを明確に記載する必要があります。たとえば、勤務先の種類には、児童発達支援センターや放課後等デイサービス、児童養護施設、保育所、障がい児入所施設などがあります。
そして、児童指導員としてどのような役割を担当し、具体的にどのような業務を行ってきたかを詳細に記述しましょう。たとえば、個別支援計画の作成や療育プログラムの実施、保護者面談、記録作成などがあります。
また、課題や問題を抱える子どもに対して、どのような支援を行ったことで成長したのかを具体的なエピソードを交えて記述します。数値で示せる成果があれば、積極的に記載しましょう。
過去に、多職種(保育士や理学療法士など)との連携において、どのような役割を果たし、どのように貢献してきたかを具体的に書きます。たとえば、合同カンファレンスでの意見交換や連携による支援の質の向上などが挙げられるでしょう。
自己PR欄で児童支援員の熱意と専門性を融合させる
400
児童支援員の自己PR欄には「なぜ児童支援の仕事を選んだのか」を語りましょう。子どもの成長を見守りたい思いや発達支援への関心、困難を抱える子どもを支えたい信念など、基本的な動機を伝えましょう。
そして、自身の強みを児童支援の専門性と結びつけてアピールします。たとえば「子どもの気持ちを十分に理解し、安心感を与えることができる明るい性格と、発達心理学などの知識に基づいた適切な関わり方が強みです」のように、具体的な知識や経験と結びつけて説明しましょう。
強みの説明後、これまでの経験で得た学びと自身が成長したと感じるエピソードを具体的に伝えます。これまでの経験とは、困難な事例を通して学んだことやチームとの連携を通して得た気づきなどです。
最後に、応募先の施設への貢献意欲を明確にしましょう。 施設の理念や特徴的な取り組みをしっかりと把握し、自身の経験やスキルをどのように活かし、貢献したいかを明確にします。
児童支援員の職務経歴書の各項目の書き方
職務経歴書の各項目には、基本的な書き方があります。そこで、児童支援員の職務経歴書の各項目の書き方について、詳しく解説します。
日付・氏名
日付は、面接・持参する日、または郵送する日を右寄せに記載しましょう。履歴書と同時に提出する場合は、日付を統一する必要があります。
氏名は、戸籍通りに書きましょう。苗字と氏名の間は、1文字分スペースを開けて書くとバランスよく書けます。
そして、氏名の下には住所・連絡の取りやすい電話番号・メールアドレスを記入しましょう。
職務概要
職務概要とは、採用担当者が要約した過去の職務経歴を見て、たくさんの応募の中から限られた時間で理解してもらうための欄です。
そのため、過去の職歴について簡潔に4〜5行程度(100〜300前後)にまとめる必要があります。
具体的には、これまでの経験で力を注いできたポイントやそれに紐づく実績などです。
児童支援員に特化した職歴が過去に複数ある場合は、時系列順に沿って作成しましょう。また、企業名は運営元法人から、正式名称で書く必要があります。
職務経歴
職務経歴について以下のように詳しく記載しましょう。
職務経歴を記載するポイント
・具体的には勤めていた企業の会社概要
・勤務先(所属していた法人名・事業所名)
・事業サービス内容
・所属・職種
・利用者人数・職員人数
・雇用形態
・雇用期間
・具体的な業務内容(わかりやすく簡潔に箇条書きでまとめる)
職務経歴が多い方は、応募先の法人・職務に関係するもの、アピールポイントになりそうな職歴を選定する必要があります。また、児童支援員以外の職歴は、その他経験として最後にまとめましょう。
やむを得ない短期職歴の場合は、家族の転勤や転居、出産などと退職理由を書いても問題ありません。
活かせる経験・知識・技術/資格
活かせる実績経験があれば具体的に記入しましょう。上司や部下、保護者から評価された経験を記載するとよいです。
児童支援員で役立つ知識やスキルがある際は、箇条書きでまとめましょう。具体的には、以下のとおりです。
児童支援員の転職に活かせる経験やスキル
・安全管理と対応力
・企画力とコミュニケーション能力
・学習支援能力
・協調性とチームワーク
・心理ケアノウハウ など
また、資格がある際は、取得年月順に正式名称で記載する必要があります。
自己PR
職務経歴書の自己PRは、児童支援員になってアピールしたいことを200〜400字の文章でまとめます。書く流れとしては以下のとおりです。
自己PRを書く手順
1.児童支援員に対する思い
2.これまでの経験でどのようなことを学んだか
3.経験を踏まえて児童支援員としてどんなことをしたいか
4.やりたいことを自分のスキルがどのように活かせるか
自己PR・志望動機が思い浮かばなくて困っている時は、以下の記事も参考にしてみてください。
【就職版】児童支援員の職務経歴書の自己PR例文

新入社員で児童支援員に就職する際の、自己PR例文を紹介します。
【就職版】自己PR例文
私は、子どもたちが安心して成長できる環境を提供したいという考えから、児童支援員を志しました。子どもたちが自分らしく過ごし、可能性を広げられるような関わりを大切にしたいと考えています。
大学では心理学を専攻し、発達支援について学びました。ボランティア活動では、子どもとの信頼関係を築くことの大切さや、個々に合った関わり方を実践的に学びました。
これらの経験を活かし、貴法人では子ども一人ひとりに寄り添いながら、安心できる環境づくりに貢献したいと考えています。私の強みである傾聴力や観察力を活かし、子どもたちが心から安心できる支援を行いたいです。
児童支援員としての熱意を示し、学校や地域活動で得た知識・スキルをアピールします。また、子どもたちに寄り添う姿勢を強調し、自身の強みであるスキルを活かして貢献したいことを伝えましょう。
関連記事:新卒でも職務経歴書は必要?求められた場合の対応や確認方法を紹介
【転職版】児童支援員の職務経歴書の自己PR例文
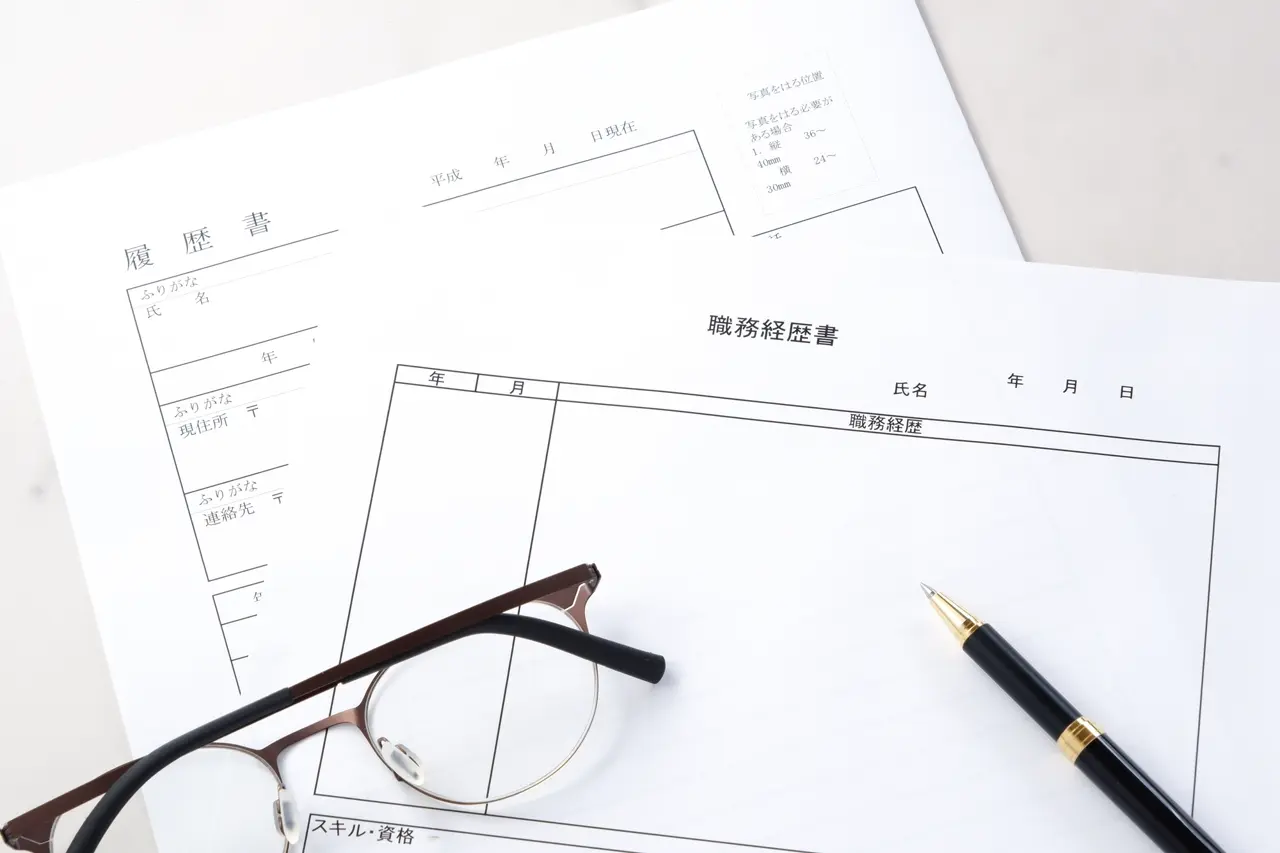
児童支援員に転職する際の、自己PR例文を紹介します。
【転職版】自己PR例文
私は前職で接客業に従事しており、お客様とのコミュニケーションを通じて相手の立場に立って考える力を養いました。これらの経験を活かし、より人と深く関わる仕事がしたいと考え、児童支援員を志しました。
児童支援員を志したのをきっかけに、子どもと関わるボランティア活動を行っています。ボランティア活動では、一人ひとりの個性を尊重しながら、信頼関係を築くことの重要性を学んでいます。また、問題が発生した際には冷静に対応し、適切なサポートを行う力も身につけました。
貴法人では、これまでの接客業で培った対人スキルを活かし、子どもたちや保護者と信頼関係を築きながら、安心できる環境づくりに貢献したいと考えております。
前職の経験を活かして児童支援員を志望する理由を明確にし、対人スキルや課題対応力が役立つことを示します。そして、ボランティア経験を加え、子どもや保護者と信頼関係を築いたことを伝えると信ぴょう性が増すでしょう。
児童支援員の職務経歴書でよくある質問

職務経歴書を書く際に疑問や不明点があらわれます。そこで、児童支援員の職務経歴書でよくある質問をまとめているので、詳しく回答していきます。
保育士としての経験しかないのですが、児童支援員の職務経歴としてどのように書けば良い?
職務経歴書には、担当した年齢や発達段階、具体的な保育内容、保護者との連携状況などを詳しく書きましょう。具体的な保育内容とは、個別対応や発達課題への取り組みなどです。
保育士としての経験は、子どもへの理解や発達支援の基礎、保護者対応など、児童支援員の業務に共通する部分が多くあります。とくに、障がいのある子どもの保育経験や、気になる子どもへの配慮などを具体的に記載すると、児童支援員としての能力が高いと評価されるでしょう。
学校や学童保育でのアルバイト経験はどのように書けば良い?
担当した学年の学習支援や生活指導などの支援内容、子どもたちとの関わりで工夫したこと、保護者との連携などを具体的に記載しましょう。
学校や学童保育での経験は、子どもたちの成長に関わる貴重な経験です。とくに、発達に課題のある子どもへの対応経験があれば積極的に書く必要があります。
経歴にブランクがある場合、どのように説明すれば良い?
ブランクの理由を正直かつ簡潔に説明しましょう。ブランク期間中に何をしていたかを具体的に伝えることで、意欲を示すことができます。
具体的には、育児や資格取得のための勉強、スキルアップのための研修、療養などが挙げられます。たとえば、以下の記載例を参考にしてください。
ブランクの書き方の例文
・育児経験は、子どもの発達段階への理解を深めるよい機会になった
・資格取得のために専門知識を学んだ
上記のように、ポジティブな経験を記載するとよいでしょう。
障がいのある子どもへの支援経験はどのように書けば良い?
障がいのある子どもへの支援経験は、以下の内容を記入しましょう。
支援経験の例文
・障害の種類(発達障がい、知的障がいなど)
・障がいの程度
・具体的な支援内容
・支援方法(TEACCH、PECS、SSTなど)
・医療機関・療育機関との連携経験
具体的な支援内容は、個別課題への取り組みやコミュニケーション支援、日常生活動作の支援、感覚統合的なアプローチなどを記入しましょう。
特別な配慮が必要な子どもへの対応経験はどのように書けば良い?
特別な配慮が必要な子どもとは、気になる行動を示す子どもや不安定な子ども、虐待や貧困など困難な環境にいる子どもなどです。特別な配慮が必要な子どもへの経験は、具体的な対応方法や連携した関係機関、意識したことなどを記載しましょう。
上記のように順序よく詳しく書くことで、採用担当者に理解してもらえる文章作成ができるでしょう。
児童支援員の職務経歴書作成をマスターしよう

本記事では、児童支援員の職務経歴書の書き方について、具体的なポイントや注意点を解説しました。
職務経歴書は、自身の実績や能力を採用担当者に伝えるための大切な書類です。実績や役割を具体的に記載し、応募先の求める人物像に合致する内容にすることが大切です。
職務経歴書の作成に不安がある方は、履歴書作成サービス「ワンポチ」がおすすめです。スマホやパソコンで簡単に作成できるため、ぜひご利用ください。
ワンポチには児童支援員向けの職務経歴書テンプレートがあります。簡単に作れる職務経歴書に興味がある方は、ぜひ一度お試しください。
職務経歴書だけでなく、児童支援員の履歴書の書き方も自信が無い方は、以下の記事を確認してみてください。
転職活動に慣れていない方や、しばらく転職活動から遠ざかっていた方は、まず履歴書と職務経歴書の基本的な書き方を確認することから始めましょう。
履歴書・職務経歴書のパソコン・手書き・スマホの作成方法のメリット・デメリットが知りたい方はこちら!
基本の志望動機・自己PRの書き方は、以下をクリックしてください!