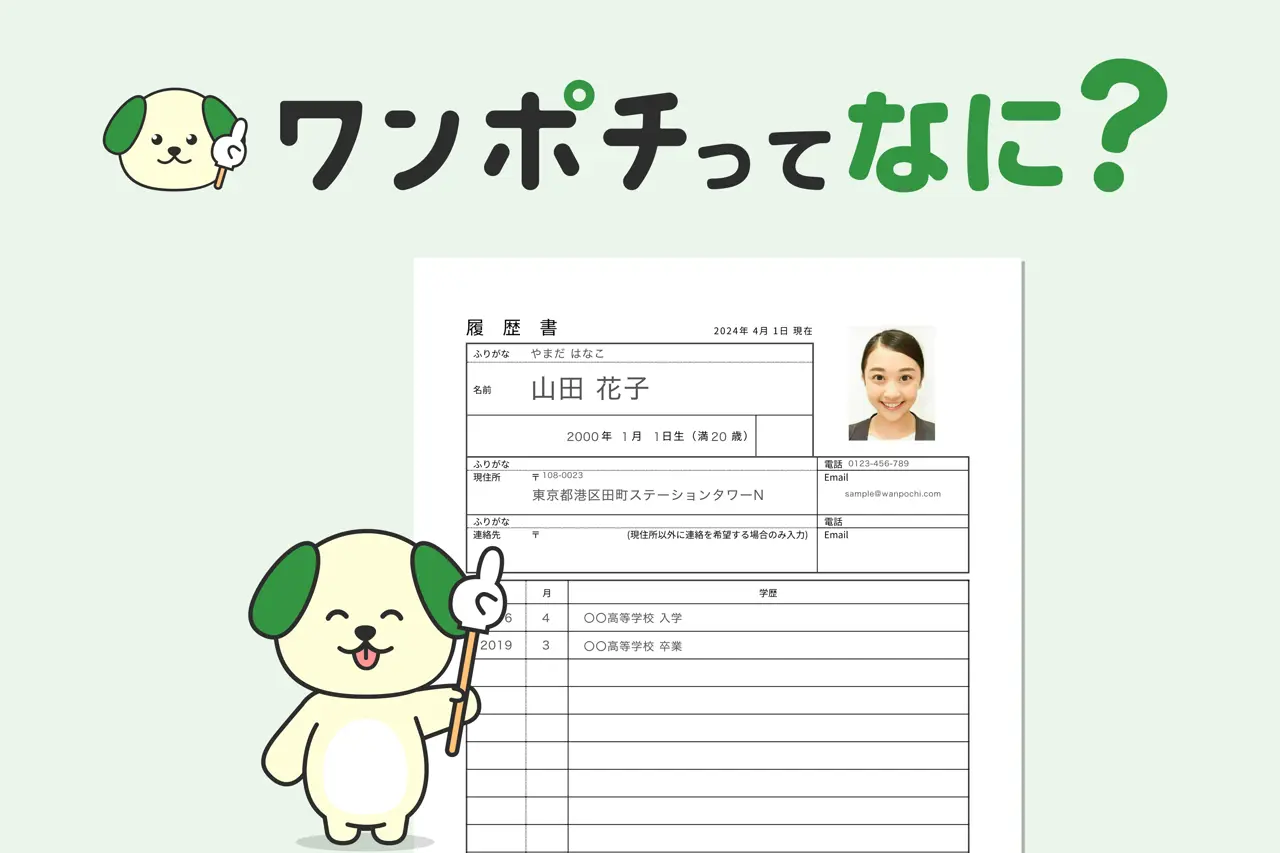転職活動は何から始める?事前準備から入社までの流れを詳しく解説

今後のキャリア形成をしていくうえで、一念発起して転職を考えている人も少なくないでしょう。しかし、実際に転職活動をするとなると「何から始めるのかわからない」という人もまた多いのではないでしょうか。転職活動を成功させるためには、事前にしっかりと準備を行っておく必要があります。
本記事では、転職活動を始める前に行う事前準備から、スケジュールの立て方、現職の退職手続き、転職先への入社までの流れを詳しく解説します。
履歴書・職務経歴書簡単作成ツールのワンポチを使ってみる
転職活動は何から始める?

転職活動は何から取り掛かればよいのでしょうか。どのように進めていけばよいのかよく理解できていない状態で、情報を集めたり、書類作成に入ったりしているケースもあるでしょう。まず、転職活動における全体の流れと、事前準備ついて解説していきます。
転職活動のおおまかな流れ
転職活動は、一般的に以下の順番で進めます。
1.全体スケジュールの計画
2.自己分析、キャリアの棚卸し
3.情報収集
4.書類作成・応募
5.面接
6.内定・退職・入社準備
まず転職の事前準備として、自己分析、キャリアの棚卸し、情報収集にそれぞれ1週間ほど時間をかけます。その後、書類作成・応募に約2週間、選考・面接に約1カ月程度かかるのが一般的です。
最終的に内定が出て、現職の退職手続きや業務の引き継ぎ、転職先への入社までに1カ月が目安となっています。人によって転職活動の期間は異なりますが、準備を開始してから転職活動を終えるまでの期間は平均して3〜6カ月と考えておくとよいでしょう。
以下では、この転職プロセスについて一つずつ詳しく説明していきます。
転職活動にかかる期間
学生時代の就職活動と異なり、転職活動は自分のタイミングかつ一人で行う必要があります。転職においては、求人が出されるタイミングは企業ごとに異なり、求職者自身も自分の状況によって活動のタイミングやスケジュールを考えなければいけません。就職活動と違って、転職するか、現職にとどまるかという判断も自由です。
転職活動においては実際の仕事経験やスキルが評価対象とされ、新卒の就職活動時に期待されたポテンシャルや将来性などの評価割合は大きく下がります。基本的には、採用側が中途採用で求めているのは即戦力の人材です。転職活動では内定から入社の意思決定、勤務開始までの期間が短いのも特徴といえるでしょう。
以下の見出しで、転職活動の流れを一つずつ説明していきます。
【STEP1】全体スケジュールの計画

まず転職活動の最初のステップとして、全体スケジュールの計画を立てます。どのように計画するかは人それぞれですが、計画的に転職活動を進めたい人は「逆算スケジュール」がおすすめです。
逆算スケジュールでは、先にゴールとなる転職予定日を決めてから、それ以前のスケジュールを設定します。転職活動の期間をだらだらと間延びさせないためにも、明確なゴールの設定は重要です。
ノープランで進めた際の失敗例として、「何となく応募先を選んでしまう」「勢いで転職先を決めてしまう」といったケースが挙げられます。現職の退職手続きや引き継ぎとの兼ね合いもあるため、転職は計画的に行い、現職のメンバーへ迷惑がかからないよう配慮が必要です。
【STEP2】自己分析、キャリアの棚卸し

全体スケジュールを立てたら、次に自己分析とキャリアの棚卸しを行います。
「コミュニケーション能力」や「リーダーシップ」といったポータブルスキルはどの業界にも通用するため、これらの強みが応募先でどのように生かせるかまで一連の流れを準備しておきましょう。
転職目的を整理して「自分の軸」を明らかにする
自己分析は、仕事をするうえでの「自分の軸」を明らかにするために必要なプロセスです。自分の軸が明確であれば、複数社に内定をもらった場合などの判断基準となります。
「コミュニケーション能力」や「リーダーシップ」といったポータブルスキルはどの業界にも通用するため、これらの強みが応募先でどのように生かせるかまで一連の流れを説明できるよう、準備しておきましょう。
自己分析を行えば、自分の軸や志向性がクリアになり、転職先の選択肢も広がってくるでしょう。
これまでの経験を振り返りアピールできる自分の強みを確認する
アピールしようと考えている自分の強みと、自己分析した結果に矛盾がないかを確認しておく必要があります。これは、入社後の働き方のギャップを無くすために必要です。例えば、「スピーディーな判断ができる」とアピールしたくても、自己分析した結果が「慎重にものごとを考える」では、採用後にミスマッチが生じてしまいます。
また、できる限り多くの情報を掘り起こして整理しましょう。これまであまり意識していなかった、思いもよらないアピールポイントが見つかる可能性もあります。自分では過小評価している経歴も、企業にとっては評価対象になる場合があるため残らずピックアップしておきましょう。
【STEP3】情報収集

自己分析・キャリアの棚卸が終わったら、情報収集に入ります。企業が求める人物像と自身の特性や活かせる強みを擦り合わせるうえで重要なプロセスです。情報収集が不十分な場合、志望動機や自己PRを考える際に行き詰まってしまう可能性があるため、入念に行いましょう。
情報を集める方法
情報収集の手段や利用できる支援サービスとしては以下が挙げられます。
・転職サイト
・転職エージェント
・転職イベント
・ビジネスSNS
・コーポレートサイト
・業界新聞・専門誌
転職サイトで探したり、転職イベントで直接企業と接触したりする方法が代表的なものでしょう。
転職エージェントを活用すれば、専任のキャリアアドバイザーが自分のキャリアに合った求人を紹介してくれます。企業とのコミュニケーションもサポートしてくれるため、はじめての転職活動に不安を感じている場合も安心です。
これらのほかにも、気になる企業や業界があれば、公式サイトなどから直接情報を拾うのももちろんOKです。
応募を検討する職種や業界を理解する
応募先の企業情報だけでなく、その企業が所属する業界の情報もインプットしておけば理解が深まります。特に異業種への転職の場合、働き方を具体的にイメージするためには企業研究が必須です。以下の項目は最低限チェックしておくべきでしょう。
創業(設立)年 | 業歴が長い企業ほど社内体制が整備されている。新しい企業はチャレンジできる機会が多い。 |
資本金 | 資本金が多い企業は対外的な信用力が高い。一概には言えないため同業他社と比較するのが望ましい。 |
業績(売上・収益) | 過去3〜5年の実績を確認する。業績の悪い会社は離職率も高い傾向にある。 |
従業員数 | 従業員数が少ない企業は離職率が高まりやすい。同業他社と比較し妥当性を確認する。 |
本社・事業所の所在地 | 通勤時の参考にする。複数の勤務先がある場合、転勤の可能性も確認する。 |
事業内容、主力商品・サービス | 自分が関心を持てる内容かを確認する。顧客の立場で商品やサービスに魅力を感じるかも重要。 |
強み・独自性 | 同業者と比較して、企業独自の特色・強みがあるかを見る。 |
企業理念 | 事業内容や企業の方針に沿った内容かを確認する。 |
社風・雰囲気 | 職場環境が自分にマッチするかどうかを見る。企業の口コミサイトなどを確認するのもよい。 |
募集条件を事前に確認する
入社時の雇用・契約条件や、どの程度の知識・スキルが求められるのかを知るうえで、募集条件の確認は重要です。入社後のミスマッチを防ぐためにも、最低でも以下の点は必ず確認しておく必要があります。
- 募集職種
- 雇用形態・契約期間
- 給与・諸手当・社会保険
- 求められる知識・スキル
給与・諸手当・社会保険など社内制度に関しては、企業によって大きく異なるため、現職と比較してどうかといった点も参考に確認しましょう。また、求められる知識・スキルも、入社後にギャップが生じないように実際の内容と照らし合わせながら見る必要があります。
【STEP4】書類作成・応募

情報収集・整理ができたら、書類作成・応募を行っていきます。作成する書類は主に「履歴書」と「職務経歴書」です。応募する際に準備しておきたいアイテムについても解説するため、参考にしてください。
作成すべき書類
転職時には、「履歴書」と「職務経歴書」を作成する必要があります。履歴書には、学歴や職歴など自分の基本情報を記載します。職務経歴書は、これまでの職務経験や実績、スキルを記載する書類です。加えて、クリエイティブ職を志望している場合には、作品をまとめたポートフォリオの用意も必要になってきます。
書類を送る際にはマナーとして送付状を添えておくと、丁寧な印象を持ってもらえます。送付状とは書類を郵送する際の挨拶状で、要件、同封する書類と枚数、そのほか伝えておきたい情報を挨拶とともに記載します。
転職サイトに登録する際にも、履歴書や職務経歴書と同じ情報を登録する必要があるため、複数のサイトに登録すると手間がかかる点は注意が必要です。
履歴書の書き方を項目ごとに解説!記入例や注意点も紹介
応募前に準備しておきたいアイテム
転職活動を進めるにあたって、以下のアイテムの準備は必須です。
- 個人のメールアドレス
- PC(パソコン)
- 個人の携帯電話・スマートフォン
- スケジュール帳
すでに持っていれば、新たに準備する必要はありません。ただし、スマホやPCの動作が遅いと企業とのやり取りに支障が出るため、応募前に修理や買い換えを検討しましょう。
最近ではオンライン面接も増えているため、必要に応じてWebカメラやマイクも準備しておくとより安心です。
自分の軸に沿った企業を探して応募
応募前の準備が整ったら、転職サイトやコーポレートサイトなどを通じて志望企業にエントリーします。中途採用の場合、応募期間が設定されていたとしても、必要な人員を確保できた段階で募集が打ち切られてしまうケースが大半です。自分にマッチした求人を見つけたら、早い段階でエントリーしましょう。
大企業や有名企業ばかりを狙って応募するのではなく、あくまで自己分析の結果に基づく自分の軸で選ぶのがポイントです。
【例文付き】履歴書の志望動機の書き方は?基本のステップと特に重視したいポイントを解説
【履歴書】印象に残る自己PRの書き方とは?強み別・職種別の例文も紹介
【STEP5】面接

エントリーした企業の書類選考に通過したら、面接案内の連絡があります。緊張や不安もあるかもしれませんが、ここまでの対策がしっかりなされていればそこまで心配する必要はありません。面接時の対策と注意点について解説するため、その点だけおさえておきましょう。
面接での注意点と対策
面接は転職活動において直接企業にアピールできる唯一の場でもあり、重要なステップでもあります。
企業によって面接の回数は異なりますが、内定が決まるまでに2〜3回程度行われるのが一般的です。一次、二次と面接の段階を経るごとに、企業の現場担当社員や人事など面接官も変わり、最終面接になると役員や社長が直接面接するケースも多いです。
いずれにしても重要なのは、「企業が求める人物像に自分がマッチしている」というアピールです。緊張やプレッシャーがあるかもしれませんが、事前準備が何よりの対策になります。面接が苦手な人は模擬面接を受けて対応力を磨き、本番で堂々と話せるよう準備しておきましょう。
面接での適切な質問の方法
面接時には、「何か質問はありますか?」と逆質問を求められるケースがあります。何を聞けばよいのかわからず困ってしまうかもしれませんが、逆質問は絶好のアピールチャンスです。
ここでも「企業が求める人物像にマッチしている」という点を踏まえて質問するのが重要です。質問例としては以下が挙げられます。
- 御社で仕事をさせていただく前に勉強しておいた方がいいことはありますか?
- 新しいことに挑戦したいのですが、新規プロジェクトへの立候補制度はありますか?
- チームワークを重んじています。社員同士が交流できる機会はありますか?
また、以下のような質問は避けましょう。
- 事前に調べれば分かる内容
- 面接官が既に話したこと
- 会社や仕事内容には触れず、給与や休日、残業時間について質問
- 面接官が答えられない、答えにくい質問
【STEP6】内定・退職・入社準備

志望企業の内定をもらい、入社意思を決めたら、現職の退職手続きを進めます。転職先の企業、現職の会社双方の手続きをタイミングをみて行わなければならないため、余裕を持ったスケジュールが必要です。それぞれの流れをみていきましょう。
内定後の準備と確認すべきポイント
無事に面接の選考を通過できたら、企業から内定連絡が届きます。あらためて労働条件や業務内容、入社日を確認し、問題がなければ承諾の回答をしましょう。
内定が出たものの入社を保留・辞退したい場合は、隠さずに理由を伝え、保留であれば入社意思がある旨を伝えておきます。その後、入社を決めた際には、内定承諾書を企業へ返送する必要があります。
内定式や懇親会を入社に先立って行う企業もあるため、参加の案内があった際は忘れずに出席可否を伝えましょう。
内定後の引き継ぎと入社準備
転職先への入社が決まったら、現職の会社に退職する旨を伝えます。具体的な退職日は、退職の意志を伝えてから1〜2カ月後が一般的です。就業規則で明確な期日が定められているケースが大半であるため、その内容も確認しておきましょう。
退職手続きを進めつつ、並行して業務の引き継ぎや後任探しを行います。退職するからといって、引き継ぎがおろそかになるとトラブルにもつながりかねません。自分の担当部署や関わっていたプロジェクト業務については、責任を持って引き継ぎを行いましょう。
また、礼儀として、現職でお世話になった社員へのあいさつ回りも忘れてはいけません。退職時には上記の引き継ぎや、行う手続きも多いため、余裕を持ったスケジュールが必要です。
退職のタイミングと注意点
退職時期は、繁忙期や携わっているプロジェクトの進行中は避け、引き継ぎの時間が十分にとれる時期を設定します。無計画に転職活動を進め、途中で仕事を投げ出してしまう形は避けましょう。
転職活動を始めてから、転職先へ入社するまでには早くても3〜6カ月かかるのが一般的です。この期間を踏まえて、退職するタイミングを逆算しておきましょう。
退職までのスケジュール管理
転職先企業への入社を決めたら、現職の企業を退職する必要があります。具体的な退職日は、大体1〜2カ月後が目安です。法的には、退職日の2週間前までに退職の旨を申告するとされています。
ただし、引き継ぎなどを考慮すると、2週間では不十分なケースが大半です。円満退職を望むのであれば、スケジュールに余裕をもって退職の意思を伝える必要があります。現職でお世話になった方へ、退職前には忘れずにあいさつをしましょう。
転職先へ入社するにあたっての準備
空白期間を設けずに転職先へ入社する場合は、特別な手続きはありません。現職を辞めてから入社までに期間が空く場合には、健康保険の切り替えと、国民年金への切り替え手続きが必要です。
また、入社する企業から税務手続きのために「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「年金手帳」などの書類を求められることがあります。
用意する書類や提出するタイミングは企業によってさまざまです。入社前や入社後すぐに提出を求められても困らないように、事前に問い合わせて必ず確認しておきましょう。
転職活動を始めるタイミングはいつ?

転職活動を始めるタイミングは、「働きながら転職活動する場合」と「会社を辞めてから転職活動する場合」の2パターンにわけられます。それぞれのメリット、デメリットをみてみましょう。
働きながら転職活動する場合
働きながら転職活動をする大きなメリットは、経済的な不安を抱えなくて済むという点です。
精神的に余裕をもった転職活動ができ、キャリアにも空白期間が生じないため、採用する側に「職歴にブランクがある」と不安を抱かれる心配もありません。
働きながら転職活動をするデメリットとしては、時間の確保が難しいという点です。就業時間内に転職活動を行うのは、職務専念義務違反にあたる可能性が高く、懲戒処分の対象になります。そのため、転職活動は業務時間外や休日を使って行う必要があり、応募先企業の面接の日程調整が大変です。
また、転職活動を行っていることを周囲に知られてしまうと、職場に居づらくなるケースもあるため注意しましょう。
会社を辞めてから転職活動する場合
退職後に転職活動をするメリットは、転職活動に十分な時間をかけられる点です。応募先企業とのスケジュール調整も行いやすく、自己分析や履歴書の作成、面接の準備も徹底できます。余裕を持って準備できれば、結果的に転職活動をスムーズに進められます。
一方、退職後に転職活動をするデメリットとしては、転職先が決まるまで安定した収入がなくなるという点です。キャリアの空白期間ができるため、活動が長期化するほど応募企業に与える印象が悪くなってしまい、選考において不利になります。
退職後に転職活動する場合、転職理由やキャリアプランはもちろん、なぜブランクができてしまったのかも明確に説明できるようにしておきましょう。
転職活動で困った時にはどうすればいい?

転職活動をしている人全員が何の問題もなく活動を進められるわけではなく、悩みや不安を抱えながら転職活動を行なっている人の方が多いでしょう。ここでは、転職活動で困った時の対処法について紹介していきます。
ハローワークを活用する
転職活動で悩む場合、ハローワークを活用する方法があります。ハローワークを活用する際のメリット、デメリットをみてみましょう。
ハローワークのメリット | 求人数が多く、相談や面接対策も受けれる
ハローワークは求人数が多く、特に地元の求人やハローワークにしかない求人がある点がメリットです。職業安定法によって「公共職業安定所は求職者に対しできる限り就職の際に住居の変更を必要としない職業を紹介する」と定められているため、地元の求人が多くなっています。地元で転職したい、転居を望まない人は、ハローワークで求人を探すのがよいでしょう。
また、ハローワークでは無料で相談や面接対策も受けられ、失業手当も同時に手続きできます。これから転職活動を始めるという場合は、一度相談してみてください。
ハローワークのデメリット | ハローワークは現地に行く必要があり、相談員によって対応が変わる可能性もある
デメリットとしては、求人の閲覧や手続きのために直接ハローワークに出向く必要がある点です。転職エージェントとは異なり、ハローワークで対応してくれる相談員は毎回同じではありません。親身に対応してくれる人もいれば、事務的な人もいるという点は留意しておく必要があるでしょう。
また、自分から積極的に行動する力が必要となり、求人情報に画像がないため社内の雰囲気がわかりにくいといった点もデメリットです。
転職エージェントを活用する
転職活動の相談先として、転職エージェントサービスを活用する方法もあります。転職エージェントもメリット、デメリットを把握したうえで活用するのが望ましいでしょう。
転職エージェントのメリット | 手厚いサポートがある
転職エージェントは、求人を出す企業が人材紹介料や成果報酬を支払って運用されているため、求職者であれば無料で登録・利用できるのがメリットです。転職エージェントサービスでは、専任のキャリアアドバイザーがつき、求人探しから入社後のアフターフォローまで一貫してサポートしてくれます。
応募書類の添削や面接対策、企業との給与交渉などを仲介してくれる場合もあり、初めて転職をする方や、在職中に転職活動をする方にとって非常に心強い存在となるでしょう。
転職エージェントのデメリット | 利用時のやりとりに手間がかかる
サービスごとに対応エリアや得意な業種・職種が異なるため、紹介してもらえる求人に偏りが出る可能性もあります。例えば、地方で転職したいが、首都圏エリアの求人紹介をメインとしている転職エージェントでは、中々希望する勤務先を見つけられないかもしれません。事前に転職エージェントの特色をリサーチした上で、サービスの登録・利用を検討しましょう。
また、キャリアアドバイザーとのやり取りが必須なため、煩わしさを感じてしまう時があるかもしれません。自分のペースで進めたい場合には、企業へ直接応募をする方法を取るのがよいでしょう。
転職活動の失敗パターン3選

転職活動には、陥りがちな失敗パターンがあります。よくある失敗事例から、回避する方法や対策を考えてみましょう。
大手企業や有名企業ばかりを検討する
なかなか内定がもらえずに長期化するパターンとして、大手企業や有名企業に固執してしまっているケースが挙げられます。
そもそも、大手企業が中途採用の募集をしているケースはそれほど多くありません。求人が自身の経験・スキルに合致するとは限らないため、選択肢は極めて限定されてきます。タイミング良く応募できても競争率が高く、選考に通過する確率は限りなく低いといえるでしょう。
何より、「大手に転職したい」「有名だから入りたい」という理由が先行してしまうと、入社した後にギャップを感じて結局辞めてしまい、転職をやり直すというケースも考えられます。今一度、転職する目的を見直してみる必要があるでしょう。
ポテンシャルや意欲だけで選考が通過できると考える
ポテンシャルや意欲はあるものの、自己分析が十分できていないという第二新卒層に多く見られるパターンです。
転職活動においては、たとえ経験が浅くてもキャリアの棚卸しをしっかり行うのが鉄則です。中途採用を行う企業は、ポテンシャル面への期待ではなく、これまでの経験やスキルなど実績を重視します。「年齢的にまだ若いから大丈夫」「やる気だけはある」とたかを括っていると、なかなか内定が出ない場合も多いため注意が必要です。
自己分析を行ってキャリアビジョンを明確にし、職務経歴書の作成や面接対策を抜かりなく行って、自身のキャリアやスキルをうまくアピールできるようにしておきましょう。
志望動機が漠然としすぎている
書類選考の段階で落ちてしまう場合、志望動機が漠然としすぎている可能性が高いです。志望動機は、「この会社に入社したい」という求職者の熱意や企業の理解度を確認するものであり、「他社でも同じことが言えるのでは?」と思われてしまうと選考対象外になってしまいます。
例えば「社風や経営理念に魅力を感じた」は、他社でも使い回せてしまう表現です。「福利厚生が充実している」「残業が少なそう」など待遇面の良さだけを志望動機にするのも避けましょう。
【Q&A】転職活動でよくある質問

何かと不安や悩みも多い転職活動においては、少しでも疑問や不明点を解消しておきたいという人も多いでしょう。転職活動でよくある質問をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
転職はまず何から始めればよい?
まずは、全体スケジュールの計画を立てながら、自己分析とキャリアの棚卸しを行います。
自己分析は、あらためて自分を見つめ直す機会となり、転職の目的が整理できて自分の軸が明確になります。キャリアの棚卸しは、職歴を時系列に書き出し、どのような成果をあげてきたか、どのようなスキルを身に付けられたかを振り返る作業です。自己分析とキャリアの棚卸しを行えば、転職活動の方向性がはっきりするため、途中で選択を迷った時の判断軸にもなります。
全体スケジュールの計画と、自己分析、キャリアの棚卸しが終わったら、求人情報の検索や業界研究などを行います。自己PRや志望動機を考えるうえで、企業の情報収集は欠かせません。選考時に最大限のアピールができるように、情報収集は入念に行いましょう。
転職活動が会社にバレないか不安
転職に関する情報は個人情報保護法で厳しく守られているため、応募先の会社から情報が漏れるケースはまずないと考えられます。応募先の企業には守秘義務があり、基本的には外部に公表されることはありません。
転職先に内定をもらって、現職の会社に退職の意思を伝えるまでは他言しないのが無難です。それでも会社に知られてしまうケースが皆無とは言い切れません。「遅刻や早退が増えた」といった、自身の言動が原因になってしまうケースもあり得るため注意が必要です。
会社に内緒で転職活動を行っているのが発覚したとしても、実際に処罰を受けたり解雇になったりするケースは多くありません。ただし、会社に居づらくなってしまったり、会社に説明を求められたりするケースはあります。もし転職活動が現職の会社に知られてしまった場合には、正直に説明して、上司も納得できる退職理由を伝えられるようにしておきましょう。
複数の企業に同時に応募してもよい?
転職活動において、複数の企業に同時に応募してはいけないというルールはありません。多くの求職者は、効率を考えて一度に複数企業へエントリーし、同時進行で選考結果を待ちます。
特に、中途採用では採用枠が埋まると求人の募集自体が終了してしまうため、むしろ希望条件に合った企業には積極的に応募するべきでしょう。どうしても入りたい企業があるという理由でもない限りは、応募企業を絞りすぎない方が内定をもらえる確率は上がります。
複数の求人にエントリーして選考が進むと、複数社から内定が出るというケースももちろんあります。応募する段階や選考の過程で志望企業の優先順位をつけておき、内定を辞退する企業にはお断りの連絡も忘れずに行いましょう。
転職活動を失敗しないためには事前準備が大事

転職において重要なのは、自己分析とキャリアの棚卸しをしっかり行う点です。事前準備が不十分な状態で転職活動をはじめてしまうと、途中でつまずいてしまいます。スムーズに転職活動を進めるためにも、目的を明確にし、計画的に行いましょう。
また、内定後も現職の手続きと転職先への入社手続きを並行して行う必要があります。本記事で紹介した転職活動の流れと押さえておきたいポイントを参考に、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
履歴書作成「ワンポチ」ではPC・スマホから履歴書・職務経歴書が作成できます。新卒・転職・アルバイト等のシーン別フォーマットで簡単入力。自己PRや志望動機の各種テンプレートはもちろん、入力内容の保存機能、作成後のダウンロードも簡単にできるので、誰でも気軽にご利用いただけます。履歴書を効率よく作成できるワンポチをぜひお試しください。
参考:かっこいい採用サイトを作るポイントやデザイン事例25社をご紹介|M'AXA
参考:【応募者爆増】かっこいい採用サイトの事例・作り方をご紹介|MEDIA EXCEED
参考:【転職サイト】おすすめ人気ランキング21選|専門家が徹底解説|Evo Work
参考:転職サイトおすすめランキング18選|口コミ・失敗しない選び方も紹介|転職connect
参考:転職エージェントおすすめを目的別に比較!独自の利用者満足度調査の結果も紹介|キャリアバディマガジン
参考:展示会の効率的な回り方とは?情報を収集するコツ|展示会営業マーケティング
参考:カスタマーサクセスへ転職するには?転職時に知っておきたい業界動向、仕事内容について徹底解説!
参考:転職先を選ぶ決め手は?企業選びに迷ったときの判断方法を解説|TASUKI
参考:休職中の転職活動。メンタル不調が不利にならないためのポイントを紹介|リワークセンター【Rodina】
参考:美容部員から転職を考える方へ。転職理由、経験が活かせる4つの職種を解説|レイズキャリア
参考:やりたいことがないと転職はできないの?やりたいことが見つからない原因と見つけ方についても解説|転職エージェントのIzul