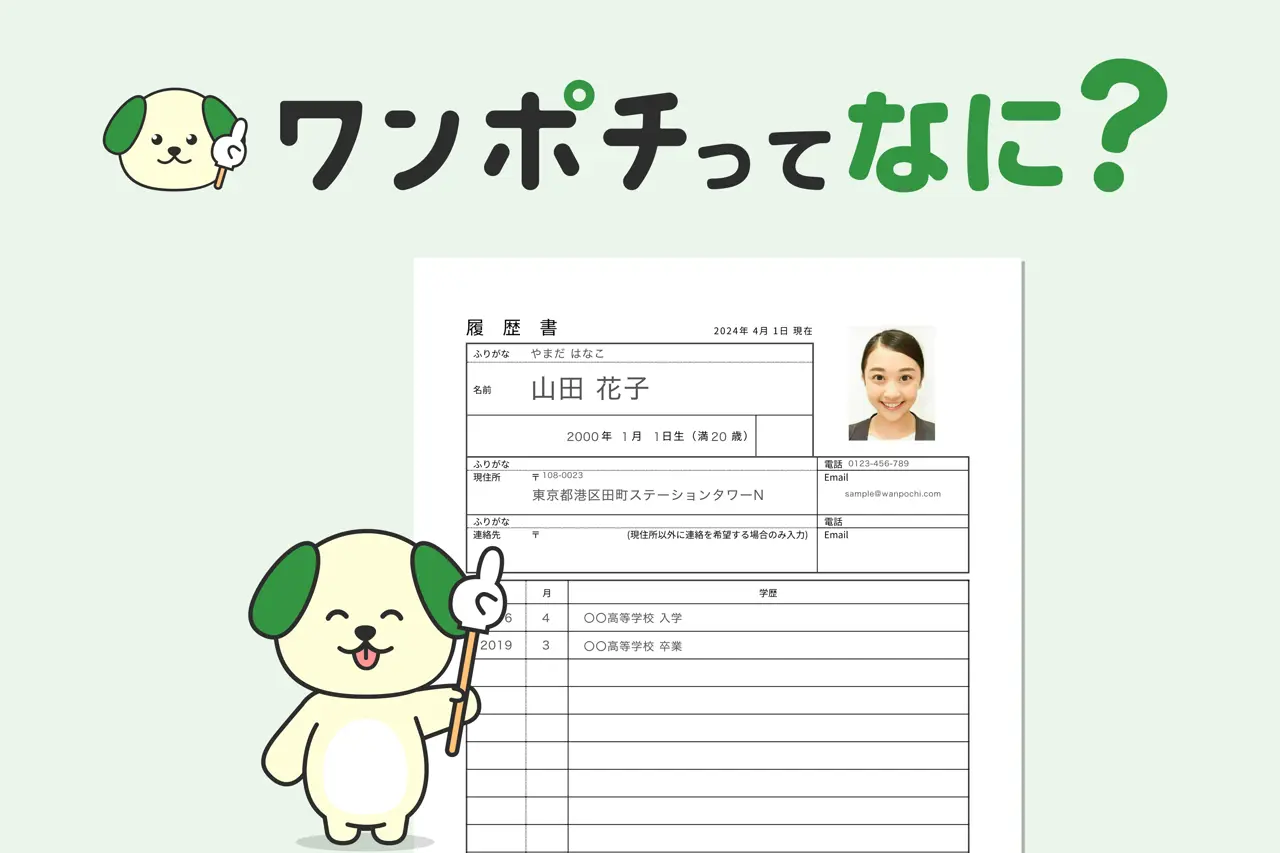退職意思の伝え方のポイント|伝えるタイミングや文例を解説
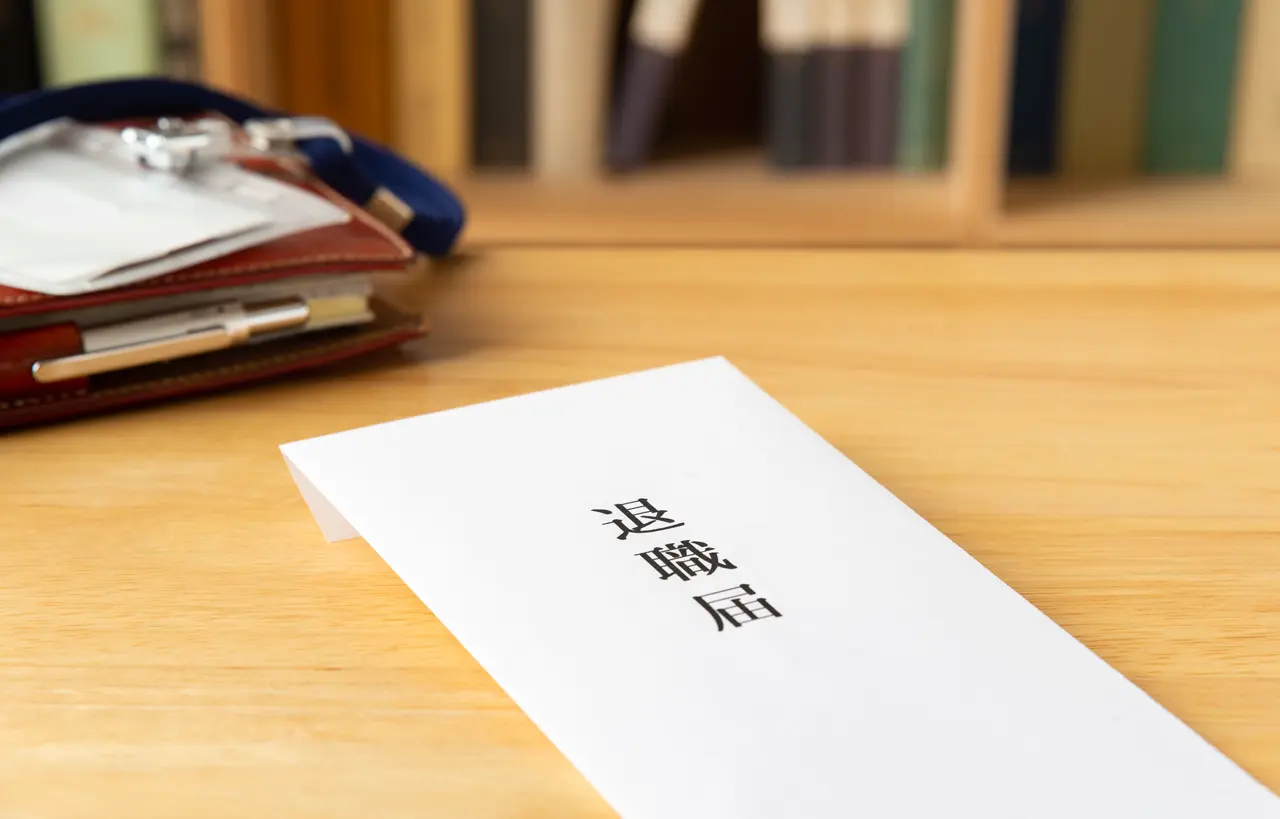
お世話になった会社を辞めるときには、できるだけスムーズに手続きを進め、円満に退職を果たしたいところです。そのためには、第一歩にあたる「退職の意思表明」に十分な注意を払う必要があります。
今回は、退職の意思を伝えるタイミングや方法について解説したうえで、ケース別の文例やポイントを詳しくご紹介します。
退職の意思を伝えるタイミング

円満退職を果たすためには、今まで勤めてきた職場にきちんと挨拶するとともに、退職を伝えるタイミングにも配慮することが大切です。ここではまず、退職を伝えるタイミングに関して、3つの注意点を確認しておきましょう。
退職を希望する日の1ヶ月以上前には伝える
民法によれば、退職の申出は少なくとも退職日の14日前までに行えばよいとされています。しかし、職場の就業規則で退職に関するルールが定められているときは、規則に従わなければなりません。
退職に関するルールは重要度が高いため、多くの企業が「〇ヶ月前までに伝える」といった形式で就業規則に記載しています。退職を検討する際には、必ず就業規則に目を通し、細かなルールをチェックしましょう。
また、仮に就業規則で明記されていなくても、退職を希望する1ヶ月以上前には伝えておくのがベターです。業務の引継ぎを含め、周囲への影響も考慮すると、少なくとも1ヶ月程度の期間は設けておく必要があります。
円満退職を果たすためには、自身が辞めた後のことも考え、影響を最小限にとどめられるような工夫と配慮が重要です。
関連記事:「仕事辞めたい」と感じる理由と退職する前に確認しておきたいポイントを解説
繁忙期や人事異動のタイミングは避ける
退職による影響を抑えるには、繁忙期や人事異動のタイミングを避けるのもポイントです。繁忙期は多くの人員が既存の業務で手一杯になるため、退職というイレギュラーな事態が生じると、普段以上に大きな負担となってしまいます。
また、人事異動の後は、すでに自身も新たなプロジェクトの人員として計算されている可能性があり、退職が大きな影響につながる恐れがあります。プロジェクトが終了した後や、人事異動が行われる前といった、できるだけ落ち着いたタイミングを見計らって伝えるように心がけましょう。
直属の上司に口頭で伝える
退職の意思は、直属の上司にアポをとり、口頭で伝えるのがマナーです。退職に関する情報は、特に重要度が高いため、普段関わりのある上司を飛び越えて広まれば不信感を抱かせる要因となります。
無用なトラブルを避けるためにも、必ず自身の管理者である直属の上司に伝えるようにしましょう。また、退職を伝えるときには、メールではなく対面で行うのが誠実です。
事前にメールで今後について相談したいことがあるため、時間をとってもらえるかを確認し、アポをとってから直接話せる機会を作ってもらいましょう。
このときには周囲への影響を考慮し、同僚がいない会議室のようなゆっくりと話せる場所を選ぶのもポイントです。
退職意思を伝えるときのポイント

退職の意思は固まっていても、いざ実際に伝えようとすると、どうしても緊張してしまうものです。スムーズに意思を伝えるためにも、事前に伝え方のポイントをおさえ、話す内容を整理しておきましょう。
退職の意思を明確に伝える
すでに退職の考えが固まっているときは、その意思を明確に表示することが大切です。会社を辞めようかどうか迷っている姿勢を示すと、引き留められたり、時間を置いて考えることを進められたりと、不本意な結論に至ってしまう可能性があります。
具体的な退職の日付は柔軟に話し合う必要がありますが、退職するという決断そのものは、ハッキリと伝えるほうが誠実です。堂々と意思表示ができるように、事前に今後のキャリアやビジョンを整理しておくとよいでしょう。
関連記事:仕事を辞めるための準備とは?トラブルを防ぐためのポイントを解説
ネガティブな理由は避けたほうがよい
退職を伝えるときには、退職に至った経緯や自身の考えにも触れる必要があります。しかし、具体的な理由については、あまりネガティブな情報に言及しないように注意しましょう。
たとえ、人間関係や給与といった会社への不満から退職するとしても、ネガティブな理由を口にすれば、心証は悪くなってしまいます。場合によっては、上司の感情を逆なでして、冷静な話し合いができなくなってしまう恐れもあるでしょう。
また、「不満な点の改善に努めるので、退職しないでほしい」と引き留められる可能性もあり、話を進めるのが難しくなります。円満に退職するためには、たとえ会社に不満があったとしても、最後まで口にしないことが大切です。
納得できる退職理由を伝える
退職理由については、できるだけ客観的に納得できるような形でまとめることが大切です。あいまいな理由では引き留められてしまう可能性があるため、スムーズに納得できるような理由を伝えましょう。
たとえば、「家族の転勤で引越しをする」「両親の介護で地元に戻る」といったやむを得ない事情がある方は、そのまま伝えたほうが話も円滑に進みます。また、キャリアアップを目指す方は、「目標だった業界に転職する」といった前向きな理由を伝えると、会社側としても送り出しやすくなるでしょう。
転職先については触れない
転職理由は明確にする必要がありますが、具体的な転職先についてあえて触れる必要はありません。現在の勤め先と転職先に接点があったときに、無用なトラブルを引き起こす原因にもなりかねないため、基本的には自分から言及するのは避けましょう。
また、同業他社へ転職するケースでは、そもそも前向きな転職理由を伝えるのが難しくなりやすいです。「より給与がいい」「休みがとりやすい」といった理由で転職をする場合、どうしても現在の職場への不満として受け取られる恐れがあります。
また、待遇面でそれほど差がなければ、「ウチのほうが良いのでは」と引き留められることもあるでしょう。そのため、転職先については具体的に触れず、「次の転職先は決まっています」と伝える程度に留めるのが望ましいです。
【例文】円満に退職するための文章例
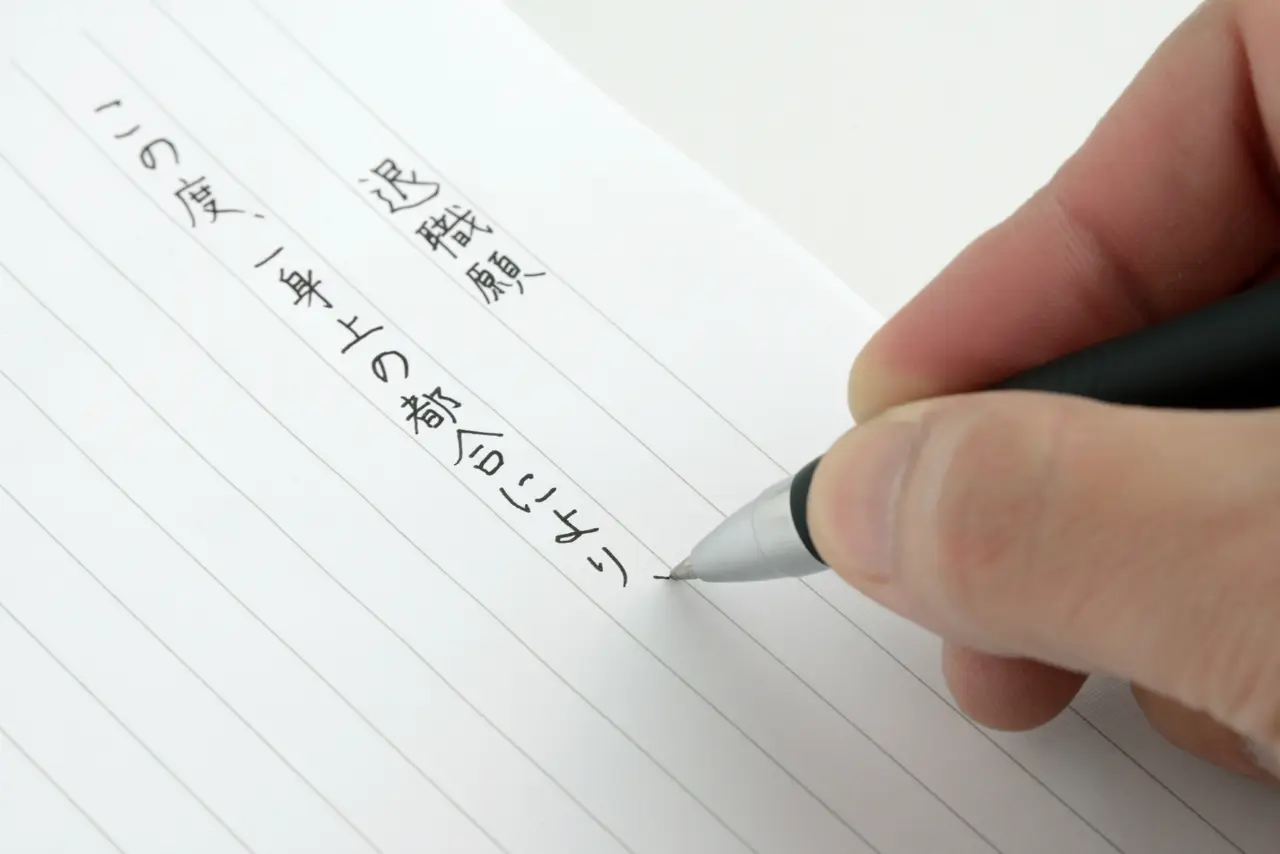
スムーズに退職の意思を伝えるためには、あらかじめどのような流れで自分の考えを表現するのか、要点を整理しておくことが大切です。ここでは、さまざまなケースを想定した退職の伝え方について、例文と要点をご紹介します。
キャリアアップの前向きな退職のケース
キャリアアップのための転職で会社を辞めるときは、ポジティブな理由を素直に伝えるとともに、応援してもらいやすくなるような工夫を凝らすことが大切です。具体的なポイントとしては、「今までの経験への感謝」「培った経験とスキルを活かしてやりたいこと」「なぜこのタイミングなのか」という3点を丁寧に説明するとよいでしょう。
伝え方の例
今まで○○の社風のもと、自分らしくじっくりと目標に向かって努力を積み重ねることができました。特に□□さんには公私ともに支えていただき、安心して成長を続けてこられたと感謝しております。
しかし、少しずつ△△のスキルが身につくなかで、徐々に自分のアイデアや技術を●●の分野でも活かしてみたいと考えるようになりました。自身の年齢とキャリアプランを踏まえると、今が挑戦する絶好の機会であると判断し、退職を決意いたしました。
仮に「今まで勤めてきた会社に将来性を感じない」「裁量が狭くてやりがいを感じられない」といったネガティブな理由があったとしても、あえて言葉にする必要はありません。ポジティブな言い換えを行うほうが、快く送り出してもらいやすくなるはずです。
健康上の理由で退職するケース
健康上の理由で退職をするときは、具体的な原因までは深く伝える必要はありません。病気や体調不良はデリケートな話題なので、特別な事情がない限りは深く追及しないのがマナーです。
しかし、場合によっては、会社側の善意で一時的な休職を勧められる可能性もあります。そのため、退職を考えているのであれば、しっかりと退職の意思が固まっているという点を伝えるのがポイントです。
伝え方の例
今まで大変お世話になりましたが、体調不良が続いており、なかなか快復の兆しが見られないことから退職を考えております。現在も毎日の通院が続いているため、退職をしてまずはきちんとと身体の調子を整えたいと思っています。誠に申し訳ありません。
健康上の理由であれば、無理に取り繕おうとせず、正直に状況を伝えるほうが円満な退職につながります。病院から診断書や治療計画書をもらっている方は、念のために持参していくとよいでしょう。
家庭の事情で退職するケース
結婚や介護といった家庭の事情による退職は、比較的に納得が得られやすいケースといえます。特に引越しをともなう事情があれば、物理的に通勤ができなくなってしまうため、その旨をありのままに伝えれば問題なく退職できるでしょう。
伝え方の例
母の介護が必要となり、家族で話し合いを持った結果、この度○○県の実家に帰ることになりました。通勤ができなくなってしまうため、退職の旨をお伝えしたいと考え、□□さんにお時間をとっていただきました。
□□さんのおかげでようやく仕事に慣れ、これから貢献できるというタイミングではありますが、どうかご理解いただけたらと思います。誠に申し訳ありません。
○○県では知人の紹介で職場が見つかりそうですので、ご心配には及びません。
これまで大変お世話になりました。
上司や会社との関係性にもよりますが、引越しによる離職では、その後の収入面を心配される可能性もあります。そのため、すでに働き口の目星がついているときは、その旨も伝えておくと余計な心配をかけずに済むでしょう。
転職先が決まってから退職するケース
すでに転職先が決まっているケースも、基本的にはキャリアアップのための前向きな退職と同様に、ポジティブな内容を心がけましょう。そのうえで、転職先の入社日が決まっているときは、退職日の相談を行う必要があります。
伝え方の例
今まで○○の社風のもと、さまざまな業務を経験させていただきました。特に□□さんには何度も相談に乗っていただき、恵まれた環境で成長できたと感謝しております。
この度、キャリアの幅を広げるために、△△の業界へ転職することになりました。それにともない、誠に勝手ながら●月末に退職をしたいと考え、□□さんにご相談いたしました。
ご多忙のところ大変申し訳ございませんが、ご検討いただけないでしょうか。
転職先が決まっていても、特に具体的な企業名を伝える必要はありません。ただし、どの業界へ挑戦するのかといった差しさわりのない情報であれば、伝えるほうが前向きな印象を与えやすくなるでしょう。
関連記事:退職届の書き方|スムーズに書くためのポイントと文例を紹介
スムーズに退職できないときの対応策

従業員の退職は、企業や組織に大きな影響を与える出来事です。十分に準備をしていても、状況や関係性によってはトラブルに陥ってしまう可能性があるでしょう。
スムーズな退職が難しいかもしれないと感じる方は、あらかじめ頭の中でシミュレーションをしておき、トラブルに発展したときの対処法を用意することも大切です。
会社から引き留められた場合
退職を伝えるときには、会社から引き留められるケースに備えて、状況に応じた結論を定めておくことが大切です。たとえば、タイミングに少し猶予がある場合は、「○○のプロジェクトが終わるまで残る」といった区切りを設けておくと、話し合いを柔軟に進めやすくなります。
しかし、すでに転職先が決まっているときは、退職を先延ばしにするわけにはいきません。「自身の人生を見つめながら何度も検討を重ねて出た結論ですので、ご理解いただけますと幸いです。」と、感謝の気持ちを伝えつつ、ハッキリと退職の意思を伝えることが大切です。
ただし、あくまでも伝える内容は感謝とポジティブな理由のみにとどめ、会社に対する不満は口にしないように注意しましょう。
話し合いに応じてもらえない場合
退職の件と分かっているにもかかわらず、直属の上司に取り合ってもらえない場合は、さらに上の役職の責任者に相談するのが近道です。あるいは、社内の人事部に相談窓口が設けられているときは、そちらを利用するとよいでしょう。
しかし、それでも状況が変わらなければ、やむを得ず労働基準監督署に相談する方法もあります。従業員の退職について、民法第627条では、次のような規定が設けられています。
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(出典:e-Gov法令検索『民法』)
退職の意思を伝えてから、2週間後には労働者側の意思で辞められると規定されているので、会社側が退職を拒むことはできません。そのため、労働基準監督署に相談すれば、基本的な問題は解消されます。
ただし、あらかじめ契約期間が決まっているときは、やむを得ない事情がない限りは期間満了前に辞めることができません。有期雇用をされている方は、ルールを混同しないように注意しましょう。
上司となかなかアポが取れない場合
上司の出張が多いときや、リモートワークで顔を合わせる機会が限られているときには、アポを取ること自体が難しいケースもあります。先延ばしにしないためにも、できるだけ早くメールで連絡を入れ、相談する時間を取ってもらえるようにしましょう。
メールを入れたにもかかわらず、なかなか連絡がこないときは、人事部に相談するのも1つの方法です。
短期退職となる場合
転職活動をして入社したものの、事前に聞いていた情報とのギャップに悩み、退職してしまうというケースはめずらしくありません。短い期間での退職は、やむを得ない事情があるケースを除き、何らかのネガティブな理由があると考えるのが一般的です。
しかし、「事前の情報と違っていたので辞めたい」と一方的に伝えると、状況によってはトラブルに発展してしまう可能性もあります。まずは、事前に提示された条件と異なるポイントを冷静に伝え、改善してもらえるか様子を見るとよいでしょう。
また、改善してもらえないときでも、会社側を一方的に非難するのは好ましくありません。円満に退職する雰囲気をつくるためにも、「自分にも確認不足の点がありました」と落ち着いて伝え、淡々と手続きを進めることを心がけましょう。
退職意思の伝え方を押さえて、スムーズな退職につなげよう

今まで働いてきた職場に退職の意思を伝えるのは、誰にとってもストレスを感じやすい場面といえます。それだけに、無用なトラブルを避けるためにも、伝え方やタイミングに細心の注意を払うことが大切です。
お世話になった職場を円満に退職し、新たなステップを気持ちよく踏み出すためにも、事前の準備とシミュレーションを丁寧に行いましょう。履歴書作成「ワンポチ」は、PC・スマホから手軽に履歴書・職務経歴書が作成できるサービスです。
各種書類のフォーマットや、自己PRや志望動機の多様なテンプレートが用意されているので、誰でも気軽にご利用いただけます。新たに転職活動を始める際は、ぜひワンポチをお試しください。
ワンポチで履歴書を作成してみたい方はこちら!
履歴書 を作成してみる